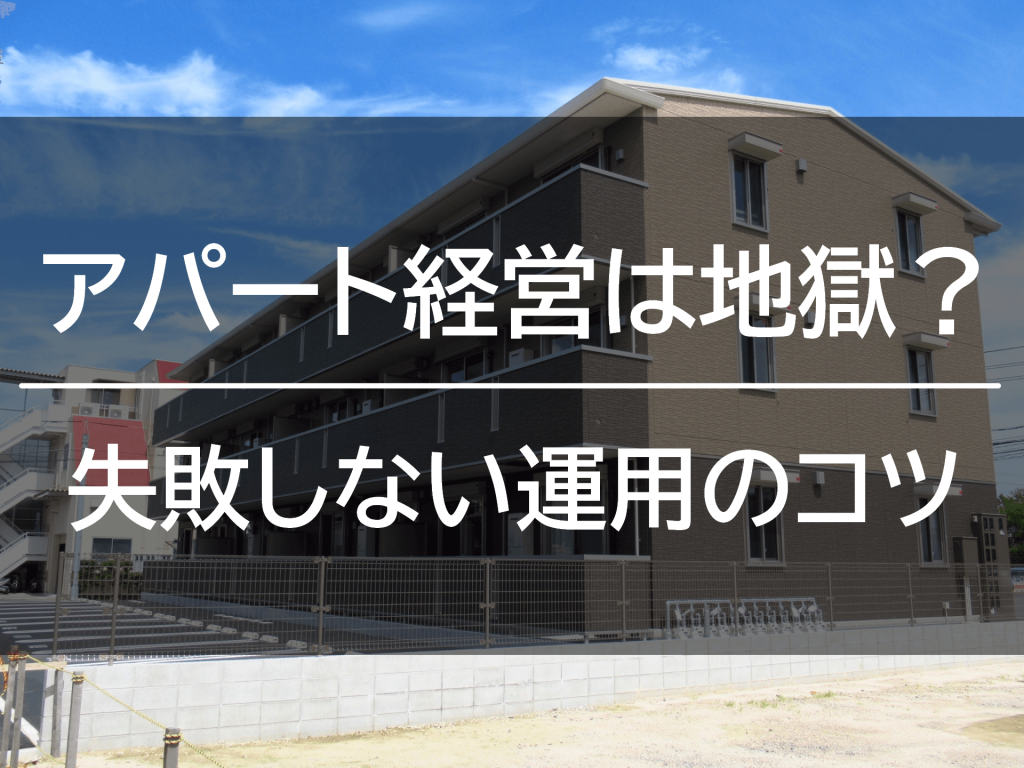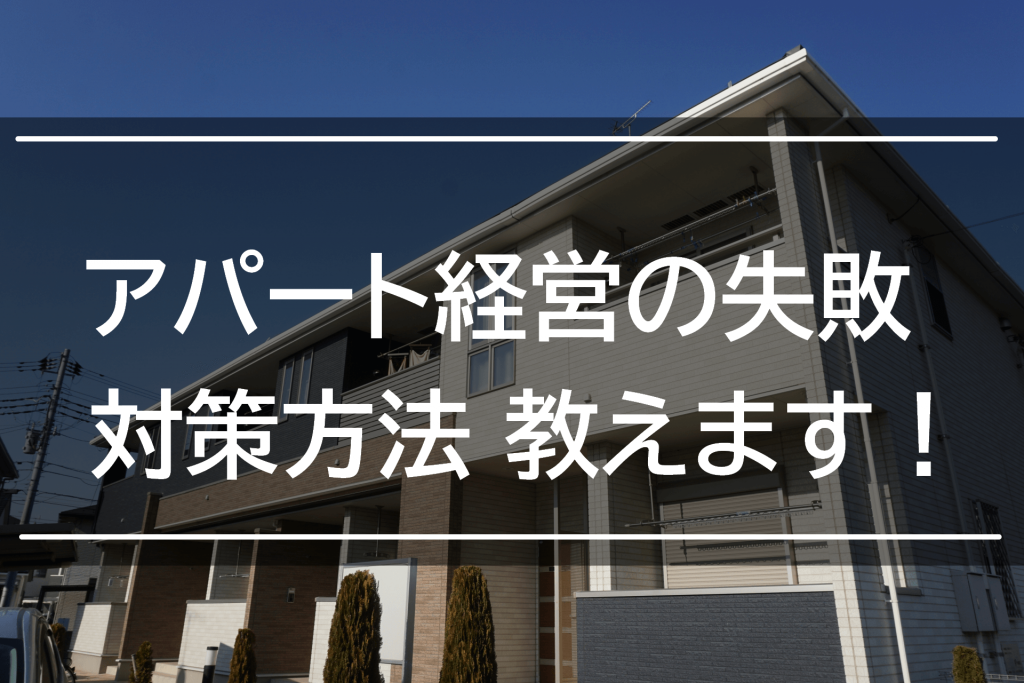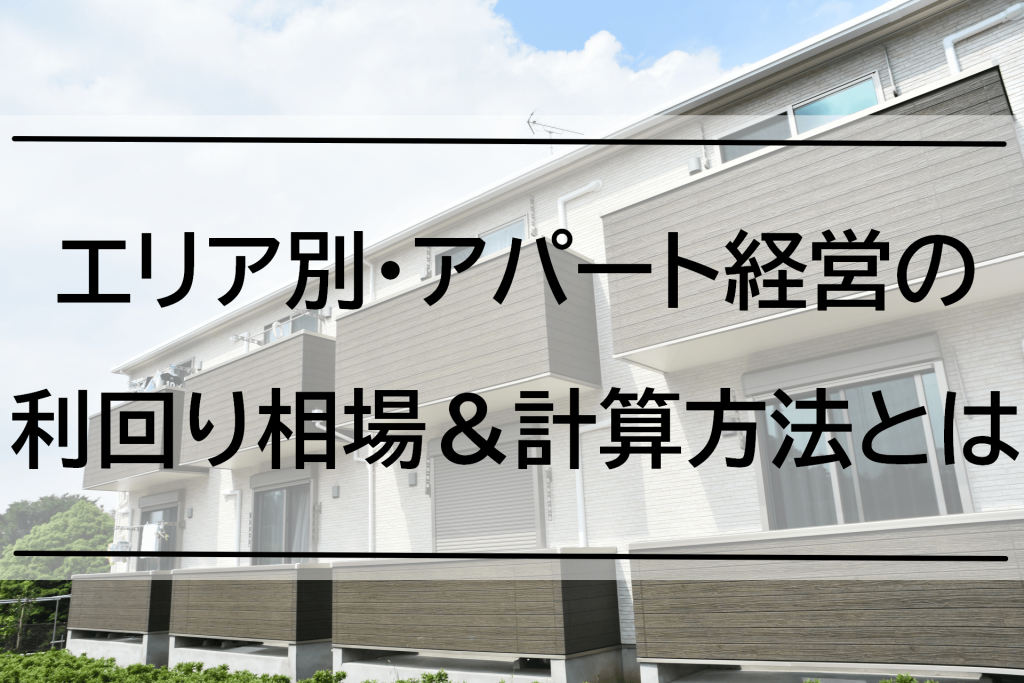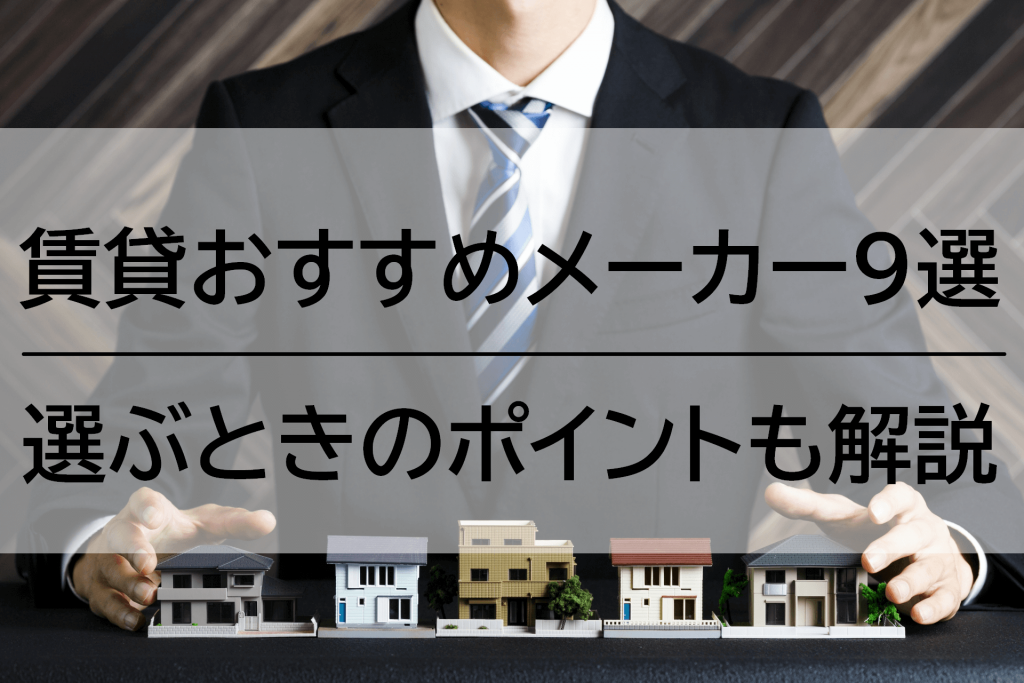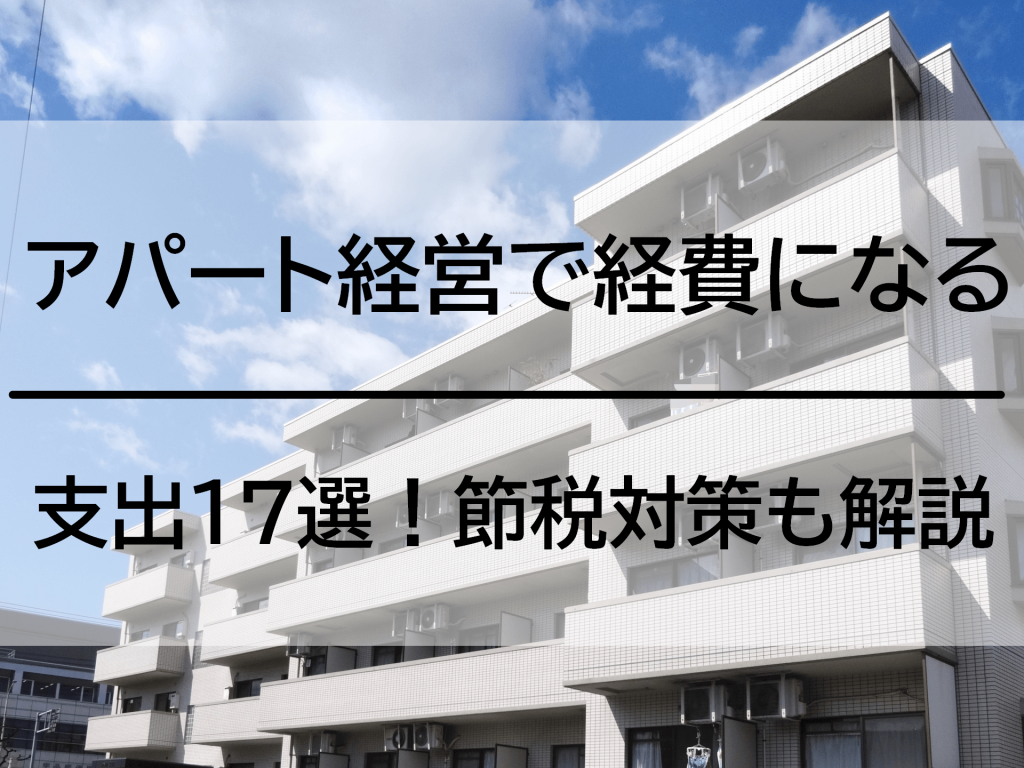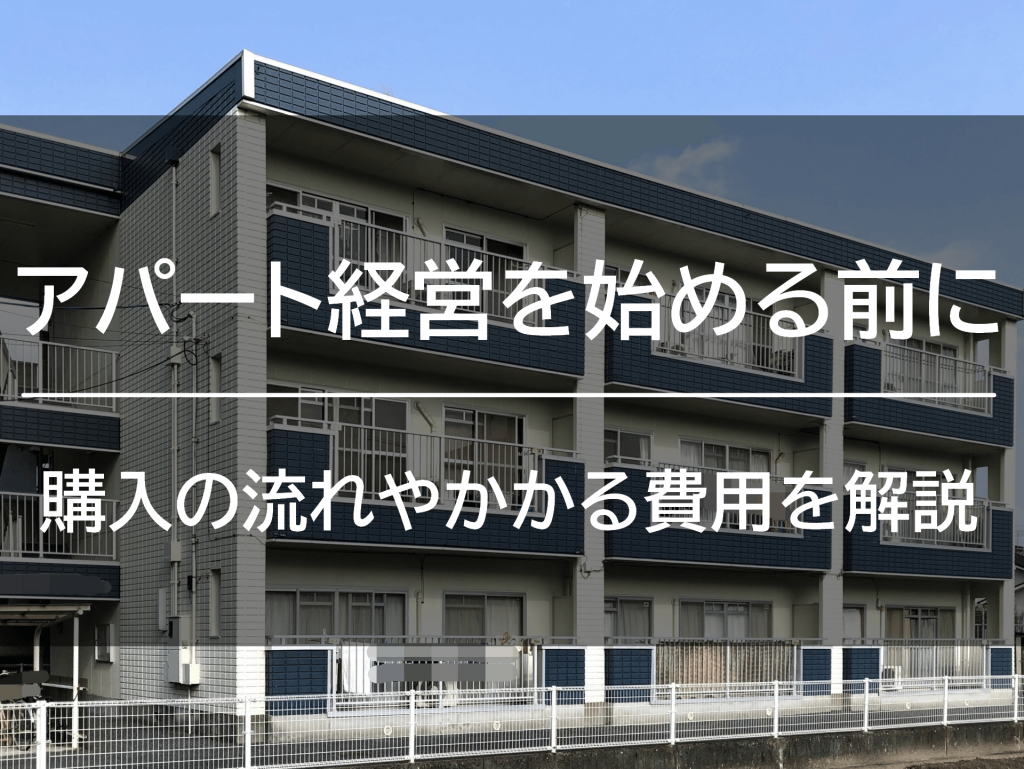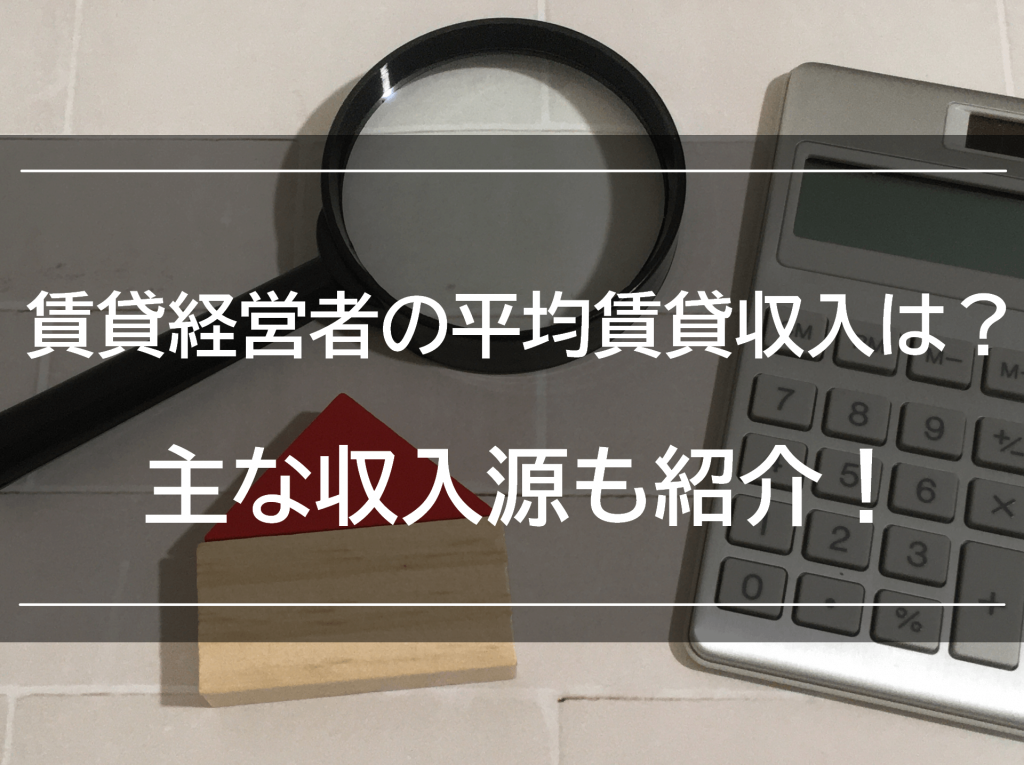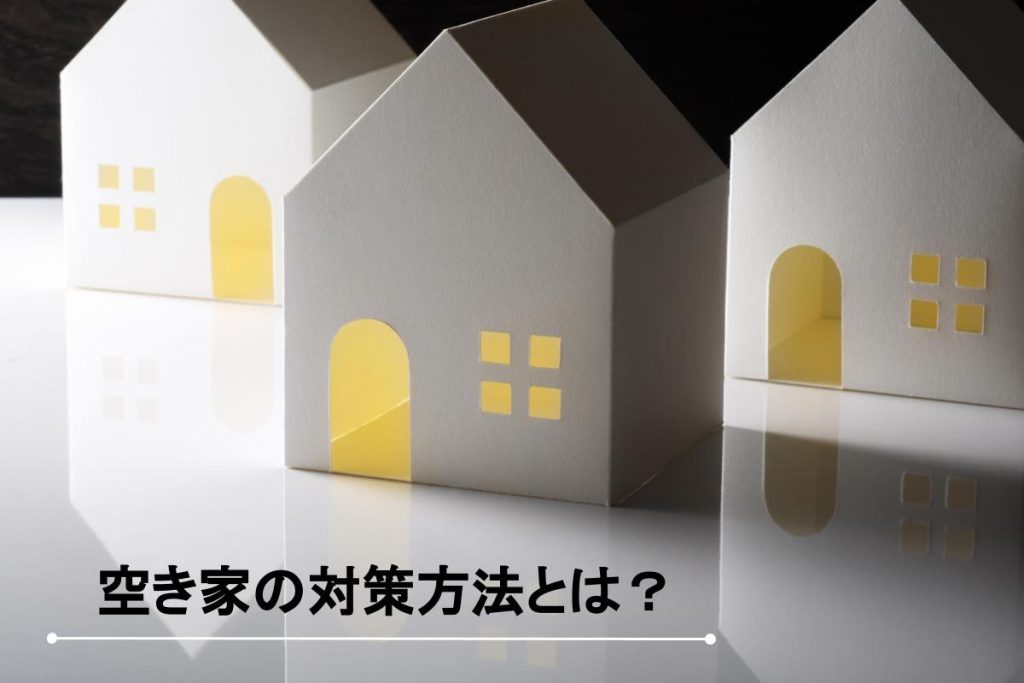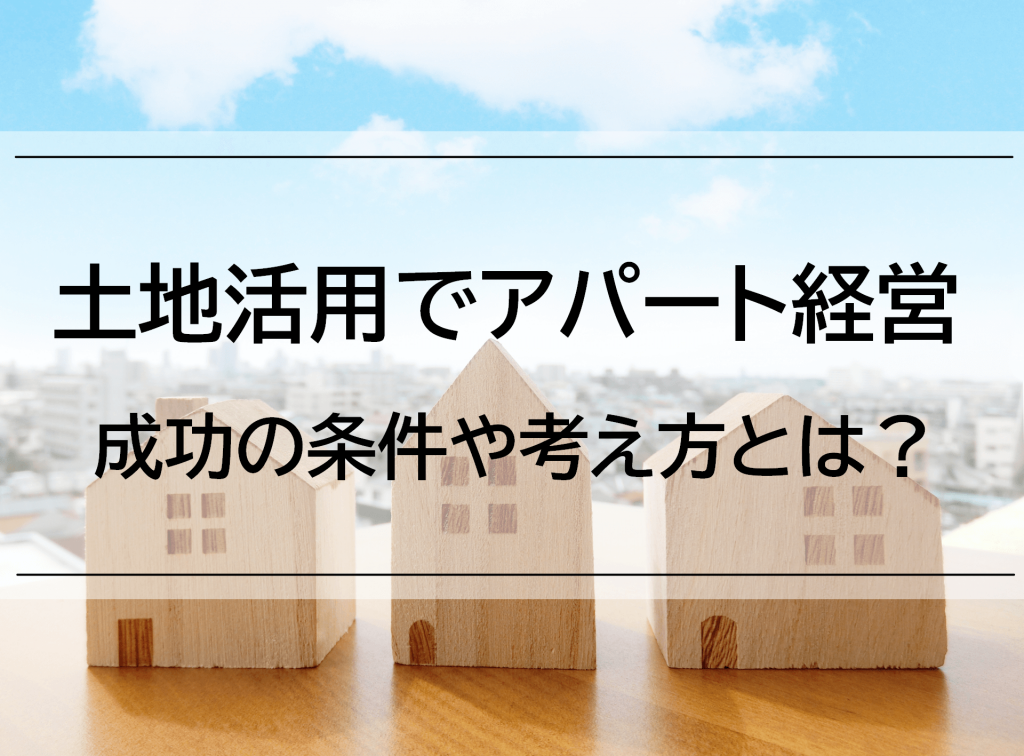※当記事はアフィリエイト広告を含みます。
「アパート経営に興味があるけど、何から始めてよいか分からない」
この記事では、これからアパート経営への参入を検討している方向けに、アパート経営の基本的な流れを解説します。
「アパート経営の不安を解消したい」「アパート経営に関する基礎知識を身につけたい」そんな方に、おすすめしたい内容になっています。この記事によって少しでも、アパート経営初心者の皆さんの不安が解消されれば幸いです。
まずはアパート経営の基礎知識を身につけよう
「アパート経営で不労所得生活を送りたい!」と夢を持つのは良いことですが、アパート経営はそんなに甘いものではありません。
これからアパート経営を始めるのであれば、まずは基礎知識を身につけることが大切です。
「アパート経営は地獄」という言葉が生まれた背景や、アパート経営がうまくいったらどの程度の利回りがあるのかなどを分かりやすく解説していきます。
アパート経営は地獄って本当?
ネットでアパート経営について調べていると、「アパート経営は地獄」という言葉を一度は目にしたことがあると思います。
その言葉は真実であり、アパート経営について調べなかった初心者が、苦境に立たされた時によく使われます。アパート経営は初心者が想像する以上にやることが多く、知識と経験のない初心者がアパート経営を始めると、失敗して地獄を見ることが多いのです。
アパート経営を地獄にしないようにするには正しい知識を身に付け、経営をサポートしてくれるプロと良好な関係を築くことが重要です。アパート経営のプロについては記事の後半でくわしく説明しますので、まずはアパート経営の基礎知識を整理しておきましょう。
なお、アパート経営が地獄になる理由と失敗しないコツについて詳しく知りたい人は、下記記事を読んでおいてください。
アパート経営は本当に地獄なのでしょうか?なぜそう言われてしまうのか、その理由や、失敗しないための対策を、具体例を交えてご紹介します。
アパート経営の成功率や利回りはどれくらい?
アパート経営の初心者が最初に気になるのは、アパート経営の成功率や利回りがどれくらいなのかという点だと思います。
とはいえ、アパート経営の成功率や利回りについては、個人投資家も含めた統計データが無いので、正確な数値は誰にも分かりません。
一方で、成功の定義や目標利回りは人によって異なるので、他の個人投資家の成功率や利回りを自らに当てはめると、アパート経営が失敗するリスクが高まってしまいます。
アパート経営が失敗するパターンはある程度決まっているため、まだ把握していない人は下記記事を読んで備えましょう。
この記事では失敗しないアパート経営のために、事前に知っておきたい失敗事例や失敗に至った理由、失敗しないための対策をご紹介します。これからアパート経営に取り組む方は、チェックしてみてください。
Jリートの実績が成功率・利回りの目安になる
他の個人投資家の実績を鵜呑みにできないとはいえ、何か参考になる数値がないと不安ですよね。そこで、アパート経営初心者の方へ成功率と利回りの参考資料として紹介したいのが、Jリート(不動産投資信託)の実績です。
Jリートを簡単に説明すると「不動産投資のプロ集団に資産運用をお願いする仕組み」のことで、運用実績は資料としてWEBで公開されています。Jリートの詳しい説明は下記リンクから確認出来るので、気になる方はチェックしてみてください。
7つのJリートで検証!プロの成功率はどの程度?
では、実際にプロが資産運用を行うJリートの実績を参照すると、どの程度の成功率があるのでしょうか。今回は、下記サイトの「Jリートダイジェスト 2020年10月版」から抜粋した、住宅系物件への投資比率が70%以上である7種のJリートについて分析します。
統計データ|J-REIT.jp | Jリート(不動産投資信託)の総合情報サイト | ARES J-REIT View
また先ほど述べた通り、不動産投資の成功の定義は人によって異なります。そこで今回は、「一定期間でオーナー(株主)の損益が黒字」になった場合を成功と定義した上で、Jリートの成功率を算出します。
| Jリート名 | 4年半後の1口 あたり増減額(※) |
運用資産種別 | 運用対象地域 | 比較開始時の1口あたり 純資産 |
比較期間中の1口あたり 分配金額の合計 |
比較終了時の1口あたり 純資産 |
| サムティ・レジデン シャル投資法人 |
24,521円 | 賃貸住宅:100.0 % | 主要地方都市:47.9 % その他地方都市:24.8 % 首都圏:27.3 % |
99,297円 2016年7月 |
29,132円 | 94,686円 2021年1月 |
| アドバンス・レジデンス 投資法人 |
60,315円 | 賃貸住宅:100.0 % | 都心主要7区:40 % 都心部:32 % 首都圏:9 % 政令指定都市等:19 % |
159,935円 2016年7月 |
53,487円 | 166,763円 2021年1月 |
| スターツプロシード 投資法人 |
40,165円 | 賃貸住宅:97.3 % マンスリーマンション:2.1 % 高齢者向け施設:0.6 % |
首都圏主要都市:72.9 % 政令指定都市:25.3 % 地方主要都市:1.8 % |
177,391円 2016年10月 |
46,670円 | 170,886円 2021年4月 |
| 日本アコモデーション ファンド投資法人 |
105,599円 | 賃貸住宅:95.0 % ヘルスケア施設:5.0 % |
東京都23区:88.4 % その他東京圏:4.1 % 地方主要都市:7.5 % |
288,145円 2016年8月 |
93,780円 | 299,964円 2021年2月 |
| コンフォリア・レジデン シャル投資法人 |
75,432円 | 賃貸住宅:96.4 % ヘルスケア施設:3.6 % |
東京都23区:92.0 % その他東京圏:2.3 % 地方主要都市:5.7 % |
165,801円 2016年7月 |
49,864円 | 191,369円 2021年1月 |
| ケネディクス・レジデン シャル・ネクスト投資法人 |
-51,502円 | 賃貸住宅:75.7 % ヘルスケア施設:21.6 % 宿泊施設:2.0 % その他:0.7 % |
東京経済圏:64.5 % 地方経済圏:34.9 % その他:0.6 % |
235,943円 2016年7月 |
50,795円 | 133,646円 2021年1月 |
| 大和証券リビング投資法人 | 28,196円 | 賃貸住宅:71.4 % ヘルスケア施設:28.6 % |
東京都23区:37.2 % 3大都市圏(東京都23区を除く):48.5 % 政令指定都市等:14.3 % |
65,538円 2016年9月 |
19,860円 | 73,874円 2021年3月 |
(※)「4年半後の1口あたり増減額」は下記の通り計算
(4年半後の1口あたり増減額) = (比較終了時の1口あたり純資産) + (比較期間中の1口あたり分配金額の合計) – (比較開始時の1口あたり純資産)
Jリートの成功率は85.7%
7種類のJリートのうち、6種類でオーナーの損益が黒字となったため、成功率は85.7%という結果になりました。
ただし、これはあくまで不動産投資のプロが運用した場合の数値です。個人投資家がアパート経営を行う場合、不動産投資のスキルや情報不足、銀行からの信用度(融資の利率)を踏まえると、成功率は70%〜80%程度と考えるのが妥当と思われます。
なお、アパート経営も含めた不動産投資の成功率はどれくらいなのか詳しく知りたい人は、以下の記事をご参照ください。
資産運用の1つとして不動産投資を始めてみたい。しかし挑戦した人がみんな成功するほど甘くはありません。成功率はどのくらいなのか、どうしたら成功率を高められるのかを知っておけば、無用なリスクを抱えることなく不動産投資を続けることができます。
Jリートの利回りは4.25%〜11.83%
続いて、Jリートの利回りを確認していきましょう。
Jリートは各物件ごとの利回りは公開していないので、総資産に対する営業キャッシュフローの比率を「みなし実質利回り」として算出します。
| Jリート名 | みなし実質利回り | 運用対象地域 | 運用資産種別 | 営業キャッシュ・フロー | 期首の総資産 | 算出期間 |
| サムティ・レジデン シャル投資法人 |
7.75% | 主要地方都市:47.9 % その他地方都市:24.8 % 首都圏:27.3 % |
賃貸住宅:100.0 % | 9,011百万円 | 116,327百万円 | 2020年2月〜2021年1月 |
| アドバンス・レジデンス 投資法人 |
5.47% | 都心主要7区:40 % 都心部:32 % 首都圏:9 % 政令指定都市等:19 % |
賃貸住宅:100.0 % | 25,030百万円 | 457,863百万円 | 2020年2月〜2021年1月 |
| スターツプロシード 投資法人 |
8.49% | 首都圏主要都市:72.9 % 政令指定都市:25.3 % 地方主要都市:1.8 % |
賃貸住宅:97.3 % マンスリーマンション:2.1 % 高齢者向け施設:0.6 % |
7,666百万円 | 90,295百万円 | 2020年5月〜2021年4月 |
| 日本アコモデーション ファンド投資法人 |
4.54% | 東京都23区:88.4 % その他東京圏:4.1 % 地方主要都市:7.5 % |
賃貸住宅:95.0 % ヘルスケア施設:5.0 % |
13,721百万円 | 301,946百万円 | 2020年3月〜2021年2月 |
| コンフォリア・レジデン シャル投資法人 |
4.97% | 東京都23区:92.0 % その他東京圏:2.3 % 地方主要都市:5.7 % |
賃貸住宅:96.4 % ヘルスケア施設:3.6 % |
12,271百万円 | 246,861百万円 | 2020年2月〜2021年1月 |
| ケネディクス・レジデン シャル・ネクスト投資法人 |
4.25% | 東京経済圏:64.5 % 地方経済圏:34.9 % その他:0.6 % |
賃貸住宅:75.7 % ヘルスケア施設:21.6 % 宿泊施設:2.0 % その他:0.7 % |
10,901百万円 | 256,665百万円 | 2020年2月〜2021年1月 |
| 大和証券リビング投資法人 | 11.83% | 東京都23区:37.2 % 3大都市圏(東京都23区 を除く):48.5 % 政令指定都市等:14.3 % |
賃貸住宅:71.4 % ヘルスケア施設:28.6 % |
26,839百万円 | 226,860百万円 | 2020年4月〜2021年3月 |
2020年から2021年にかけての1年間で7つのJリートのみなし実質利回りを計算したところ、4.25%〜11.83%となりました。
Jリートによって利回りに差がありますが、その原因の1つとして運用対象地域の違いがあります。一般的に地方物件は都市部に比べて賃料下落リスクなどが高いため、地方への投資比率が高いほど利回りは高くなる傾向にあります。
以上のような運用地域の違いに加えて、個人投資家のスキルや経験による変動があるため、個人投資家の利回りは3%〜10%が目安となります。なお、アパート経営の利回りの計算方法などについて詳しく知りたい方は、下記記事をご参照ください。
アパート経営では、どれだけの利益を得られるかは気になるポイントですよね。 判断する基準のひとつとなるのが「利回り」ですが、きちんと理解しておかないと表面上の数字に振り回されてしまいます。この記事ではアパート経営の利回りについての基礎や、計算方法を実際の数値でご紹介します。
アパート経営者の収入・所得はどれくらい?
アパート経営をすると、どの程度の収入・所得が得られるのか気になると思います。アパート経営者の収入・所得は、所有する物件の種類や数、借入比率によって大きく異なります。
具体的にイメージを持つために、2021年時点で次のアパート1棟を持っていると仮定して計算してみましょう。
| 所在地 | 東京23区内 |
|---|---|
| 物件価格 | 8,700万円 |
| 戸数 | 8戸 |
| 築年数 | 5年 |
| 構造 | 木造 |
また、ここで解説する「アパート経営者の所得」とは、次の計算式を満たすものです。
(アパート経営者の所得) = (アパート経営の収入) – (アパート経営の支出)
アパート経営の想定収入
まずは、月額賃料や空室率などを現実的に仮定した上で、アパート経営の想定収入をシミュレーションします。ここでは、自動販売機など賃料以外の収入は一切ないものとします。
上記の物件の1室あたりの月額賃料が平均7万円で、年平均空室率が10%とすると、アパート経営の想定収入は年間604.8万円となります。
| 戸数 | 8戸 |
|---|---|
| 1室あたりの平均月額賃料 | 7万円(管理費等を含む) |
| 年平均空室率 | 10% |
| アパート経営の想定収入 | 年間604.8万円 ( = 7万円 × 8室 × 12か月 × 0.9 ) |
アパート経営の想定支出
続いてアパート経営の想定支出を、最低限必要な費用項目からシミュレーションします。
以下の表にある通り8項目を費用として仮定すると、アパート経営の想定支出は年間578.7万円となります。
| 管理費 | 年間30.2万円 ※管理費相場である賃料の5%で仮定 |
|---|---|
| 法定点検費用 | 年間7万円 ※消防設備点検のみと仮定 |
| 修繕工事費用 | 年間14.4万円 |
| 原状回復工事費用 | 年間10.1万円 ※年間退去率が20%で、1室平均7万円と仮定 |
| 仲介手数料と広告料 | 年間15.1万円 ※年間退去率が20%で、1室平均10.5万円と仮定 |
| 火災保険料 | 年間60万円 |
| 固定資産税 | 年間78.3万円 |
| 借入金返済額 | 年間363.6万円 ※4,500万円を年率3.95%の17年で借入したと仮定 |
| アパート経営の想定支出 | 年間578.7万円 |
アパート経営者の想定所得
ここまで確認してきたアパート経営の想定収入から想定支出を差し引いた結果、アパート経営者の想定所得は年間26.1万円となりました。
| アパート経営の想定収入 | 年間604.8万円 |
|---|---|
| アパート経営の想定支出 | 年間578.7万円 |
| アパート経営者の想定所得 | 年間26.1万円 |
アパート経営の想定支出の内訳を見れば分かるように、今回の仮定では借入金の返済額が圧倒的に大きな支出となります。
返済を全て終えれば支出は大幅に少なくなりますが、一方で老朽化によって空室率や費用などが増加していきます。そのため、アパート1棟での想定所得は最終的に年間300万円〜350万円辺りに落ち着いていきます。
このようにアパート経営の所得は借入金に強く影響されるので、自己資金の準備など資金計画の策定が極めて重要になるのです。
アパート経営の8つのリスクを把握しよう
アパート経営には数多くのリスクがあり、挙げ始めればキリがありません。いざという時に慌てないためにも、今回取り上げる8つのリスクについて、まずはしっかり理解しておきましょう。
空室リスク
所有しているアパートの住人が退去したら空室が発生します。
アパート経営最大の収入源である賃料が減るため、最大の影響力を持つリスクと言えます。
家賃滞納リスク
マンションと比べて元の賃料が低いアパートでは、空室と並んで大きな影響力を持つリスクです。
空室を避けようとするあまり、支払い能力の低い入居者を入居させた際によく発生します。
家賃回収に時間と労力が取られるため、悪化すると裁判費用などが必要になってきます。
家賃保証会社との契約である程度防止可能なものの、保証料の支払いでさらに経営コストがかさんでしまいます。
賃料下落リスク
地方であるほど大きな影響力を持つリスクです。
空室対策のために賃料を下げて新規入居者を募集したのが既存入居者にバレて、値下げ交渉を迫られることもあります。
自然災害リスク
豪雨で土砂が流れ込んだり、地震で上下水道設備が損傷したりと、近年大きくなっているリスクです。
保険に入っていてもすぐに保険金が入金されるわけではないので、手持ちの資金で先に修繕することがほとんどです。
老朽化リスク
アパートの老朽化が進むと、外壁や給排水設備の修繕に100万円単位の費用がかかります。
資金が無いからと先延ばしして雨漏りや漏水が発生した時には、入居者からのクレーム、ひいては退去や訴訟につながる可能性もあります。
立地リスク
例えば、最寄り駅やスーパーからの距離が遠いなど、立地による不便が多いと入居者の退去率が上がってきます。
その結果、原状回復工事や入居募集広告の費用などが増加し、アパート経営費用増加へとつながってしまうのです。
入居者トラブルリスク
入居者間で騒音や人間関係などのトラブルが発生した際、オーナー側に解決するよう相談がくることもあります。
ただし、オーナー側ができるのはお願いくらいであり、トラブル発生源が無くならない限り定期的にお願いをすることになるので時間をとられてしまいます。
金利上昇リスク
景気変動によってはアパートローンの金利が上昇する可能性もあります。
近年は金利が上がる傾向はあまり無いものの、借入額が大きいと返済額にも大きく影響してくるので、注意が必要です。
アパート経営のメリットとデメリット
アパート経営にはメリットもあれば、当然デメリットもあります。両者をしっかり把握した上で、最終的な判断をしましょう。
メリット1.長期的な安定収入
今さら述べるまでもなく、アパート経営は安定収入を生んでくれます。
運営をサポートしてくれるプロ達をうまく活用すれば、高齢者になっても経営を続けられるのです。
メリット2.生命保険の代わりになる
自分が亡くなった後も物件は家族に相続されるので、生命保険の代わりにもなります。
また、ローン借入時に「団体信用生命保険」に加入しておけば、死亡や高度障害になった時に保険で借入額を支払えるので、より安心できます。
メリット3.景気変動に強い
景気が悪化すると物価は下落していきますが、アパートの賃料はすぐには下がりません。
また、物価が長期的に上がった際には、賃料増額交渉も可能となります。
メリット4.節税対策ができる
利益が出るようになったら、「物件管理」の名目で車を経費で購入したり、諸々の備品を購入して節税対策ができるようになります。
収入規模が大きくなったら個人事業主から法人に変更することで、節税できる範囲がさらに広がるのです。
デメリット1.運営管理コストが高い
アパートには多くの運営管理コストがかかります。
そして、アパートが古いほど修繕費用がかかりますし、立地が悪いほど仲介会社に支払う報酬が大きくなるなどコストが大きくなるのです。
デメリット2.大きな出費が出ることもある
アパート経営では思いがけず、大きな出費が発生することもあります。
古いアパートだと屋根や外壁、老朽化した給排水設備の修繕などで、百万円単位の出費が出ることもあります。
デメリット3.分散投資は難しい
投資対象を複数にする「分散投資」は投資の基本ですが、アパートは1棟を購入するのに数千万から億の金額がかかることがほとんどです。
アパート経営では金銭的に、分散投資するのは難しいと言わざるをえません。
デメリット4.現金化は簡単ではない
相続税の納付などで多額の現金が必要になった場合にも、アパートは不利です。
アパートを売却したくても、売却活動開始から売却完了まで数ヶ月単位の時間がかかってしまうからです。
アパート経営に向いている人の特徴
アパート経営はやることも多く、誰でも成功できるものではありません。では、どのような人がアパート経営に適しているのでしょうか。
アパート経営に向いている人の特徴を挙げてみましょう。
忍耐力がある
アパート経営では土地の購入や建物の建設から運営、そして最終的な売却まで、あらゆる場面において忍耐力を求められます。
管理会社を入れない場合は自分で草刈りや掃除をしなければいけませんし、家賃の滞納が発生したら支払いの催促をしなければいけません。
日々襲い来るストレスに対する忍耐力を持つ方こそが、アパート経営者に適しているのです。
計画性がある
資金や修繕の計画などをしっかり立てられる計画性も、アパート経営において非常に大切です。
特にお金の管理を適当にしていると銀行などの金融機関から計画性がない人物と判断されるため、ローン審査が厳しくなるので注意してください。
学ぶ姿勢がある
アパート経営では、日々新しい知識を習得する姿勢が求められます。
アパート経営は不動産に関する知識はもちろん、税務や法律まで幅広い知識が求められます。
最初から全ての知識を持っている必要はありませんが、運営しながら学んでいく姿勢がなければ、いつまで経っても経営は安定しません。
最後は相手を信頼できる
やることが多岐にわたり、専門知識も必要とされるアパート経営は、オーナーだけで全て対応するのは難しく、どこかの場面でプロのサポートが必要になります。
悪徳業者もはびこる不動産業界ではありますが、最後は相手を信頼しないと自分が苦しくなっていくのです。
アパート経営に役立つ資格7選
アパート経営自体に資格は必要ないですが、下記7つの資格はアパート経営に活かしやすいのでおすすめです。
不動産実務検定
不動産需要の有無や人口の動向から入居者トラブルの対応など、不動産実務に関する技能を計る資格です。
2級は合格率も高いので、初心者アパート経営者におすすめの資格と言えます。
初めての方へ|不動産投資資格の日本不動産コミュニティJ-REC
宅地建物取引士
不動産に関する法律である宅建業法の他、民法や建築基準法など各種の法律に精通していることが求められる、不動産業者向けの資格です。
簡単には合格できないので、身を入れた勉強が必要です。
管理業務主任者
管理組合等へ重要事項説明や管理事務報告を行うために必要な国家資格です。
マンション管理業を営む際に必要とされます。
簿記(2級〜3級)
アパート経営では確定申告をする際に各種費用の帳簿付けは必須です。
簿記も3級であれば多大な時間はかからないので、取得しておけば確定申告の際にも大助かりです。
ホームインスペクター(住宅診断士)
住宅の劣化状況や欠陥の有無、改修すべき箇所・時期、かかる費用などを見きわめ、アドバイスを行なう専門家がホームインスペクターです。
アパートの購入や売却の前に建物のコンディションを把握する能力が身に付きます。
ホームインスペクター(住宅診断士)になるには – 日本ホームインスペクターズ協会
フィナンシャルプランナー
返済計画や物件にかかる費用の計画を立てるにあたって役立つ資格です。
年金や社会保険、老後の生活設計など、アパート経営や不動産以外のお金についても幅広く知識を身につける必要があります。
中小企業診断士
その名の通り、中小企業の経営状況を診断する専門家です。
難易度は高めですが、アパート経営の状況を正確に把握するためにも、いずれは取得を検討してもよいかもしれません。
次は信頼できるプロを見つけよう
アパート経営はやることも多い上に、専門的かつ幅広い知識が必要です。一人ですべてをこなすのには限界があるので、プロのサポートを受けた方が円滑な経営につながります。
アパート経営に必要な基礎知識が身についたら、以下のような専門家で信頼できるパートナーを探しましょう。
不動産売買会社
アパートを建設する土地を所有していない場合、土地を購入してアパートを新築するか、既に建設されている中古アパートを購入することになります。その際、売買のプロである不動産売買会社に頼るべきです。
自分の足で売りに出されている土地やアパートを見つけ出すのは困難ですし、万が一見つかってもアパートを購入希望者と所有者間の手続きや交渉は非常に面倒だからです。
不動産売買会社に相談すれば、候補物件の紹介から条件交渉、書類手続きまでトータルでサポートしてくれます。
ただし、不動産売買会社といっても戸建てやアパート・マンション、商業施設など得意分野があるので、過去のアパート案件に関する実績を調べたうえで依頼するかどうかを判断しましょう。
建築会社
建設できる土地を所有していても、アパートがまだ建っていないのなら、アパートの建築会社を見つけて建設を依頼しましょう。
現地調査から始まり、設計や施工まで、工程は多岐にわたりますし、もちろん費用もかかります。竣工まで、どの程度の時間や費用が掛かるのか、事前に相談だけでもしておくことです。
もしも具体的にアパート建設を始める段階になったら見積もりを取得し、借り入れを申し込む金融機関に提出することになります。
また、アパート建築会社を探す際には不動産売買会社と同様に、アパート建築の実績が豊富な会社から選ぶようにしましょう。
大手の建設会社よりもアパートに精通している会社の方が、安くて良質な仕事をしてくれることも多いのです。
なお、賃貸アパートのおすすめメーカーについて気になる方は、下記記事もぜひチェックしてみてください。
今回は賃貸アパート建設におすすめのメーカー9選をご紹介します。依頼先を決めるときのポイントも解説するので、依頼先を決めかねている方は必見です。
銀行
アパートを建設したり購入する際に自己資金が潤沢にある場合は別ですが、多くの場合は銀行から借り入れをすることになります。
不動産売買会社や建築会社にアパートの購入や建設を相談する際に、提携している銀行を紹介されることも多いので、お任せするのも一つの方法です。
ただし、必ずしも紹介された銀行の金利が安いとは限りません。金利が高いと感じたら、自分でアパートの情報を持って他の銀行に相談することも可能です。
他の銀行に相談したい場合は、不動産売買会社や建築会社にほかの銀行に融資を依頼する旨を事前に伝えておくと、相手に不信感を与えません。
管理会社
アパートの管理はプロである管理会社にお任せするのがおすすめです。
自分でも入居者への対応はできるものの、本業があって忙しい場合や複数のアパートを所有して規模拡大を目指すのなら、全て自分だけで行うのは非常に大変です。
アパート管理会社を入れることで「水漏れが起こった」「隣の人がうるさい」「お湯がでない」といった入居者からのクレーム対応もしてくれますし、家賃の滞納が発生した際に滞納者への催促も行ってくれます。
なお、業務委託する場合、どの程度費用がかかるのか気になるところだと思いますが、通常の管理業務を行う管理会社なら、賃料合計の5%が管理費の相場となります。
建物管理会社
管理会社だけでなく、建物管理会社もアパート経営における頼れるパートナーになります。
先ほどご紹介した管理会社が入居者への対応を主な業務とするのに対し、建物管理会社は清掃や異常チェックなどを主な業務としています。
階段や踊り場の掃き掃除といった日常清掃や電気設備の点検など、アパートのハード面の維持管理をしてくれます。
アパートに清潔感が無いと入居者から苦情が入ったり、内見に来た入居希望者が辞退してしまったりすることもあります。
建物管理会社に依頼して、日頃からアパートの手入れをすることがアパート経営の成功率も高めてくれますよ。
賃貸仲介会社(客付け)
アパートから退去者が出て空室が発生してしまうと、賃料収入の低下に直結してしまいます。
早急に空室を解消するべく新しい入居者を決める必要があるのですが、その際に重要な役割を果たすのが賃貸仲介(客付け)会社です。
店舗やインターネットで入居希望者を募集し、内見対応や契約書の締結も行ってくれます。
仲介担当者も人間ですから、日頃から問い合わせにこまめに対応しておくと、優先して入居者を紹介してもらえるようになります。
大手仲介会社だと、管理会社のサービスも同時に提供していることが多いです。
内装・設備修繕業者
退去後の原状回復(入居整備)工事や漏水修繕など得意分野が修繕業者ごとにあります。
2社ほど相見積もりしながら交互に発注しておくと、費用を抑えながら関係性を維持できるのでおすすめです。
規模拡大なら必要な専門家
アパート1棟だけでなく複数棟を経営することになったら、士業との連携も検討に入れたいところです。
税理士は複数のアパートの損益計算をして必要な税務書類を準備してくれますし、積極的な税理士なら合法的な節税対策なども提案してくれます。
また、いざという時に頼りになるのが法律のエキスパートである弁護士です。家賃を滞納している入居者との交渉や退去時のトラブルがこじれた際に、法律面の相談先となってくれます。
オーナーや管理会社がお願いしてうまくいかなくても、弁護士の名前を出すだけで素直に対応する入居者は多いので、実際に訴訟をおこさなくても頼りになる存在と言えます。
経営者としての自覚を忘れずに!経営の安定に必要な知識とは
アパート経営に本気で取り組むなら、単なる大家さんとしてではなく経営者としての自覚が必要です。
常に経営者の視点から見て、アパート経営をどのように安定させるかを考えていくことが成功の秘訣です。経費や税金、かかる費用について理解を深めておきましょう。
アパート経営で経費になるものは?
アパート経営を成功させるには、節税も重要なポイントです。経費にできる支出をしっかり計上することで、余分な税金を払う必要がなくなるのです。
経費として計上できる代表的な項目は次の通りです。
減価償却費
建物(アパート)の取得費用は購入した年度に全額を計上するのではなく、「減価償却費」として、分割して計上することになります。
各種税金関連
アパートを所有しているとかかる各種の税金(固定資産税・不動産取得税・事業税・印紙税など)も、経費として計上可能です。
損害保険料
火災保険や地震保険といった損害保険料も、経費として計上できます。
ただし、複数年契約の保険に加入した場合、その年の経費にできるのは1年分のみです。
5年契約であれば保険料の総額を5分の1だけ算入できるのです。
修繕費
外壁や水道管など、アパートの修繕にかかる費用は、もちろん経費として計上可能です。
借入金利息
住宅ローンの利息分についても経費にできますが、経費にできるのは建物部分の利息のみです。
元金や土地の利息については経費とはならないので注意しましょう。
物件運営費
アパートの管理会社や仲介会社などへ支払った委託料などの、運営費用全般もアパート経営の経費にできます。
交通費
物件へ向かう電車代やガソリン代などの交通費も「交通費」として、経費にできます。
通信費
管理会社や入居者とやり取りした電話代や、物件検索に使うインターネット料金なども経費にできます。
書籍費
アパート経営に関する情報収集を目的とした新聞や書籍、雑誌の購入の費用も経費にできますが、趣味の書籍などを含めることはできません。
接待交際費
管理会社や税理士との打ち合わせなどでレストランやバーなどを利用した場合も、経費として認められます。
消耗品費
物件管理に必要なカメラやパソコン、プリンターなどの消耗品も経費計上できますが、金額によっては消耗品としてではなく、資産として計上しなければならないケースもあります。
その他
他にも、弁護士報酬や税理士報酬なども経費として計上できます。
ここまで挙げた支出でも、目的が不明確であったり私的な使用目的と明確に分けられなかったりする場合は、経費として認められないこともあります。
経費として認められなかった場合には、後で節税した分の税金を「追徴課税」として支払う必要がありますので注意してください。
判断に迷うようなら、税理士にしっかり事前に相談するようにしましょう。
アパート経営で経費になる支出について詳しく知りたいのであれば、下記記事を一読ください。
アパート経営の経費は、どこまで計上できるのか?初めての確定申告で、迷いやすい部分です。この記事では、はアパート経営で経費計上できる費用や家事按分できるもの、節税のコツと確定申告の流れを解説します。
アパート経営の主な費用と税金19種類
アパート経営では多種多様な費用と、税金がかかってきます。
どの程度の自己資金を用意するべきかを把握するためにも。物件の運営上でかかる主要な費用や税金19種類について整理しておきましょう。
アパート経営の最初にかかる費用と税金8種類
・土地購入費用又はアパート購入費用
土地やアパートを購入する費用の総額は数千万円〜数億円ほどかかるのですが、実際には金融機関かた借り入れするので、物件価格の10%〜40%である数百万円〜数千万円を自己資金として用意する必要があります。
・売買の仲介手数料
売買の仲介手数料は物件価格の3%に6万円をプラスした金額で、さら消費税もかかります。数百万円程度が目安と言えます。
・不動産取得税
土地やアパートの購入価格の60%程度が「固定資産税評価額」となり、その3%程度が不動産取得税の概算となります。おおよそ数十万円〜数百万円が目安です。
・印紙税
購入金額に対し、下記の印紙税がかかります。
- 1,000万円超5,000万円以下:2万円
- 5,000万円超1億円以下:6万円
- 1億円超5億円以下:10万円
・登記費用
登記をする際に発生する諸費用です。登録免許税や、司法書士に依頼した場合の依頼費用も含みます。
登録免許税はアパート購入の場合、固定資産税評価額の2%、新築アパートを建設した場合は地価や建築費用をベースにした価格の0.4%が税額となります。
おおよそ数十万円〜数百万円が目安となり、司法書士の報酬は数万円〜十数万円が相場です。
・ローン手数料
アパート購入や建設に関する住宅ローンの手数料には、事務手数料と保証料の2つがあり、事務手数料には借入額の1~3%または数万円の定額があります。
おおよそ数万円〜百数十万円が目安です。一方の保証料は返済期間の長さによりますが、1年増えるごとに7,000円〜1万円/年ほど増加し、15年〜22年だと十数万円が相場と言えます。
・火災保険料
補償の範囲にもよりますが、数十万円ほどが目安です。
・物件管理費用や仲介募集費用
物件の運用開始時から必要になる管理費用は、賃料の5%程度が相場です。
また、空室発生時に仲介会社へ支払う募集費用は、広告費を含めて月額賃料の1ヶ月〜2ヶ月程度が相場ですが、築年数や立地によっても上下します。
アパート経営の初期費用についてさらに詳しく知りたい方は、下記記事をご一読ください。
この記事では、アパートを購入する際の初期費用や、アパート経営の運営にかかる費用を解説いたします。アパート経営をしたいけれど迷っている方、始めるための情報を集めている方には、ぜひ読んでいただきたいです。
アパート経営の維持にかかる費用と税金11種類
・共用部分の水道光熱費
アパート階段の照明にかかる電気代や散水用の水道料金などの費用は、設備数や種類にもよりますが、毎月数千円〜1万円ほどかかります。
・火災保険料
保険の補償範囲によりますが、毎月1~10万円ほどの保険料がかかります。
・管理費
管理会社に任せる業務範囲にもよりますが、通常の入居者対応なら、家賃の5%ほどが委託料の相場です。
・所得税
アパート経営以外の収入があれば合算され、毎年の課税所得に対し5〜45%の税率で所得税がかかります。
所得税の税率は変動する可能性もあるので、下記国税庁のサイトを参考にしてください。
・住民税
住民税は地方税であるため、オーナーの居住地やアパートの立地によって税率が変動します。
目安としては所得金額の約10% + 約5,000円ほどです。
・法人3税
アパート経営者が法人化をすると、所得税や住民税の代わりに法人3税(法人税、法人住民税、法人事業税)が課せられます。
法人3税などをまとめた法人実効税率の最大は29.74%と言われており、個人の所得税が33%となる900万円超1,800万円以下の所得金額あたりが、法人化の目安になるのです。
・固定資産税
物件購入価格の約60%程度が固定資産税評価額と言われており、固定資産税評価額の1.4%が固定資産税となります。
・修繕費
アパートの築年数や老朽具合にもよりますが、修繕工事1回につき簡単な工事で数千円、水道管の更新など大がかりな工事は数十万円ほどかかります。
・原状回復工事費用
住人の退去後に原状回復工事として業者へ工事費用を支払うもので、一戸あたり数万円〜数十万円の費用がかかります。
・入居者募集費用
入居成約時に仲介会社へ支払うもので、一戸あたり賃料の半月分〜2ヶ月分ほどがかかります。
・リノベーション費
空室を埋めるためにように和室を洋室化するなどニーズに合う仕様へ変更するための工事費用で、一戸あたり数十万円〜百数十万円ほどがかります。
・大規模修繕工事費
十数年に一度の頻度で、工事1回につき数百万円〜数千万円ほどです。毎年少しずつ大規模修繕に向けて資金を積立てておくのが定石です。
アパート経営の確定申告と節税対策
アパート経営で非常に重要なのが、年1回の確定申告です。税額の大小に関わるのが「不動産所得」で、収入から経費を引いた金額のことを指します。収入や経費の例は以下の通りです。
・収入の例
家賃、共益費、礼金、更新料、駐車場代、自販機の売上
・経費の例
管理費用、募集費用、修繕費用、減価償却費、借入金の利息
※詳しくは先述した「アパート経営で経費になるものは?」をご参照ください。
また、確定申告はあくまで所得税を支払うためのものです。所得税の納税は通常であれば3月15日ですが、住民税と固定資産税は違います。
3つの税金について納付期限を確認しておきましょう。
- 所得税:3月15日
- 住民税:6月末・8月末・10月末・翌1月末(4回に分けて支払う)
- 固定資産税:市区町村によって異なる
アパート経営で必須の節税対策
アパート経営では、税金の額も成否を分ける重要なポイントです。節税対策をしっかりと行うかどうかが手元に残る資金の大小につながるのです。
主な節税対策としては、以下のような方法があります。
- 青色申告特別控除を使う
- 青色事業専従者給与を使う
- 法人化する
- 小規模企業共済を使う
- 経費計上する
- 損益通算する
青色申告を活用することで白色に比べて控除額が大きくなりますし、家族を従業員とすることで給与分を控除に充てることができます。
また、中小企業向けの保険である「小規模企業共済」の掛金は経費計上できるので、節税対策にもなるのです。
他にも事業規模が大きくなった際の法人化など、活用できる節税策はたくさんありますので税理士に相談するのもおすすめです。
アパート経営を法人化するタイミング
多くのアパート経営者は個人事業主としてスタートすることでしょう。
ただし、収益が900万円を超えているのであれば、所得税率の関係で法人化することも視野に入れるべきです。
アパート経営の維持にかかる費用と税金11種類の項目でもご説明した通り、所得が900万円以上になると個人の所得税は法人実効税率よりも高くなります。
継続的に900万円以上の所得を生み出せるのであれば、法人化をする方が節税対策になるというわけです。
アパート経営の資金計画を立てよう
アパート経営の主な費用と税金19種類の項目でも確認した通り、アパート経営には様々な費用が発生します。
そのため、アパート経営を成功させるためには、暫定的でも良いので資金計画を立てることが非常に大切です。
また、資金計画がしっかりしていると、銀行に融資を申し込んだ際にも好印象を与えることができるので、おすすめです。
そこでここでは、アパート経営者の収入・所得はどれくらい?の項目で想定したアパートを元に、アパート経営の資金計画を立ててみましょう。
東京23区内にある築年数4年の8戸アパート約8,700万円の資金計画
アパート経営の資金計画として最低限必要なのは、「初期費用と資金源の内訳」と「1年間の経営収支の内訳」の2点です。
これら2点を最低限準備すれば、数年単位のシミュレーションも簡単に行うことができます。
| 初期費用(単位:万円) | 資金源(単位:万円) | ||
| アパートの売買価格 | 8,700 | 借入金 | 4,500 |
| 売買の仲介手数料 | 267 | ||
| 不動産取得税 | 156.6 | ||
| 印紙税 | 6 | ||
| 登録免許税 | 104.4 | ||
| 司法書士費用 | 6 | 自己資金 | 4,910.1 |
| 借入事務手数料 | 95.7 | ||
| 借入保証料 | 14.4 | ||
| 火災保険料 | 60 | ||
| 項目 | 費用(単位:万円) | 収入(単位:万円) |
| 賃料 | – | 604.8 |
| 管理費 | 30.2 | – |
| 法定点検 | 7 | – |
| 修繕工事費 | 14.4 | – |
| 原状回復工事費 | 10.1 | – |
| 募集費用 | 15.1 | – |
| 火災保険料 | 60 | – |
| 固定資産税 | 78.3 | – |
| 借入金返済額 | 363.6 | – |
| 合計 | 578.7 | 604.8 |
資金計画については建築会社や不動産売買会社が提供してくれる物もあるので、それらを活用して銀行と打ち合わせをするのも1つの方法です。
また、アパート経営を始めるなら資金はいくら必要なのか気になる方には、以下の記事も参考になります。
この記事では、なぜアパート経営の自己資金比率が最低でも20%必要なのかという根拠について解説していきます。また、アパート経営の初期費用やローンの頭金なども紹介するので、しっかり読み進めてくださいね。
アパート経営のローン(借入)で知るべきこと
資金計画の項でも確認した通り、アパート経営においてローンは非常に大きな影響力を持ちます。
アパート経営のローン(借入)の審査で重視されるポイントや融資を受けるまでの流れなど、事前に理解しておきましょう。
借入の審査で重視される2点
金融機関がアパート経営の資金を融資するかを決める際には、以下の2点がもっとも重視されます。
・借入者の属性や信用情報
融資を申し込んだ人の職業といった属性や、年収や資産状況、個人識別情報などの信用情報は融資の可否を検討する上での重要なポイントです。
万が一アパート経営がうまくいかなかった場合でも融資した資金が返せるあてがあるのか、判断するというわけですね。
・物件の価値や収益性
アパートが建っている(建てる予定の)エリアや資産価値、どのくらいの収益を生みそうなのかも融資判断の大事なポイントになります。
例えば、駅やスーパーからの距離が近く住宅需要が高い地域であれば高家賃でもすぐに空室が埋まるので収益が見込める(融資した資金を回収できる)という判断になります。
借入するまでの流れ
アパート経営の融資を受ける場合、次の流れで借り入れまで進みます。
・事前相談
アパートの購入や建築を決断した段階で行うのが事前相談です。
金融機関へアパートの図面や資金計画などをまとめた事業計画書と、自分の収入や保有資産をまとめた資料、その他の借入状況の資料などを提出します。
この時点で、融資可能かどうかが大まかにわかります。
・申込み
事前相談の時点では揃わなかった資料や、金融機関からの修正依頼を受けて直した資料がまとまり次第、正式な借り入れ申込みを行います。
図面や事業計画書はもちろん、物件の登記簿謄本や公図・測量図を提出します。
さらに、本人については、確定申告書や他の借入金資料、所有不動産資料などを提出することになります。
・事前審査
金融機関が独自に物件(アパート)の調査や人物評価を行い、借入可能金額を算定します。
・事前承認
売買契約や建築請負契約の前に、事前承認という形で借入可能額や条件などを提示されます。
・本審査
アパートの売買契約(購入の場合)や建築請負契約(新築の場合)の締結後に、契約書や重要事項説明書の写しを銀行に提出することで、いよいよ本審査へと移行します。
事前審査と齟齬がないか、個人の信用情報に問題(ローン滞納や返済不能の履歴)はないかを金融機関が最終確認します。
・本承認
本審査の結果に問題がなければ、事前承認で提示された条件で融資が承認されます。
もしも問題が見つかった場合は事前承認から条件を変更になったり、最悪取り消しになったりすることもあります。
・金銭消費貸借契約の締結
本承認された条件で金銭消費貸借契約を正式に締結し、契約書に両者捺印します。
この時点でついに、借り入れ金の入金日が確定となるのです。
・入金
借り入れ金が入金されるためには、担保となるアパートの抵当権の設定が必要です。
そのため、入金日はアパートの引渡し日となることがほとんどです。
入金と同時に所有権移転や保存の登記、抵当権設定の登記も行われることになります。
ローンの金利相場と返済期間
アパート経営で利用する資金の借り入れをする際に利用することになる「アパートローン」の金利の相場は以下の通りです。
- 地方銀行:1.5~4.5%
- 都市銀行:1%
- 信用金庫・信用組合:2.5%
- ノンバンク:3~4.5%
- 日本政策金融金庫:1~2%
都市銀行の方が地方銀行や信用金庫よりも金利が安いのですが、その分審査も厳しいのが難点です。
また、金融機関によって貸し出しの限度額も異なりますので、必要な金額と自らの信用力(収入や預貯金)を加味しつつ、どの金融機関に融資を申し込むか決めましょう。
なお、アパートローンの返済期間は、一般的に法廷耐用年数以下となります。
- 木造:22年
- 鉄骨(軽量):27年
- 鉄骨(重量):34年
- 鉄筋コンクリート:47年
金利と返済期間のバランスが取れているか
金融機関を選ぶ際に、金利だけではなく返済期間も考慮して選ぶのが、借り入れを失敗しないコツです。
金利が低くても返済期間が短いと毎月の返済額が大きくなってしまい、キャッシュフローが悪化してしまいます。
たしかに金利は安いほど良いのですが、金利は費用として計上できるので、返済額とのバランスを見て決めましょう。
アパート経営が相続対策になる3つの理由
「アパート経営が相続対策になる」と言われることが多いのですが、それは次の3つの理由からです。
相続税評価額が現金よりも低い
土地部分は現金の約8割程度、建物部分は現金の約6割〜7割程度となっており、アパートとして持っておくことで現金よりも課税の対象となる相続税評価額が低く抑えられます。
相続税評価額の減額特例がある
地域にもよりますが、アパートを他者へ貸し出すことで相続税評価額が9〜27%ほど減額されます。
また、宅地であれば一定面積分の相続税評価額を最大80%削減できるという特例も利用できます。
借入金により全体の相続税評価額が下がる
不動産の相続税評価額は取得時の時価の約8割程度で評価されるため、不動産取得に使った借入金の約2割を、他の相続税評価額と打ち消すことができます。
アパート経営でよくある質問
最後に、アパート経営についてよく受ける質問をまとめました。誰もが最初は初心者で不安を抱いています。
ここで解消できないことは、専門家に聞くなどして早めに解決してしまいましょう。
アパート経営は地獄と聞くけど本当?
アパート経営は知識と準備ができていないと本当に地獄となります。
アパート経営で失敗しないコツを知りたい人は、下記のアパート経営が地獄になる理由と対策をまとめた記事を読んでください。
アパート経営は本当に地獄なのでしょうか?なぜそう言われてしまうのか、その理由や、失敗しないための対策を、具体例を交えてご紹介します。
アパート経営の利回りはどれくらい?
住宅系に投資する7個のJリートの平均利回りは4.25%〜11.83%でした。
初心者を含む個人投資家全体の平均利回りは同程度以下が予想され、3%〜10%あたりを目安にするのが無難です。
アパート経営の成功率はどれくらい?
住宅系に70%以上投資するJリートを分析したところ、約5年の期間で収益をプラスにできたのは7個中6個でした。
不動産投資のプロ集団が成功率85.7%なので、スキルも信用も不足している個人投資家全体の成功率は、70%〜80%あたりが推定されます。
中古アパート経営はおすすめできる?
土地を持っていないのであれば、安価で購入できる中古アパートを購入して経営するのもおすすめです。
ただし、アパートの築年数によっては、借り入れの審査が通らない場合もあるので注意が必要です。
アパート経営とマンション経営の違いは?
アパート経営とマンション経営の大きな違いは運営規模です。
マンションの方が基本的に運営規模が大きくなり、求められるスキルや経験も増えていきます。
ただし、マンションの一室のみを投資するワンルームマンション投資は、アパート経営よりも少額からお手軽始められます。
アパート経営のセミナーには参加すべき?
アパート経営のセミナーは全国各地で行われているので、興味があるものは参加してみましょう。
参加することで経営を始めたり続けたりするためのモチベーションを高めたり、経験者の苦労話などから学べたりというメリットがあるのです。
アパート経営の基礎知識を身につけよう
ここまで、アパート経営に関する基本的な情報を幅広くお伝えしてきました。
日々知識をアップデートすることで、アパート経営の成功率は高まります。
参考記事や書籍などで知見を貯めて、万全の状態でアパート経営を始めてくださいね。