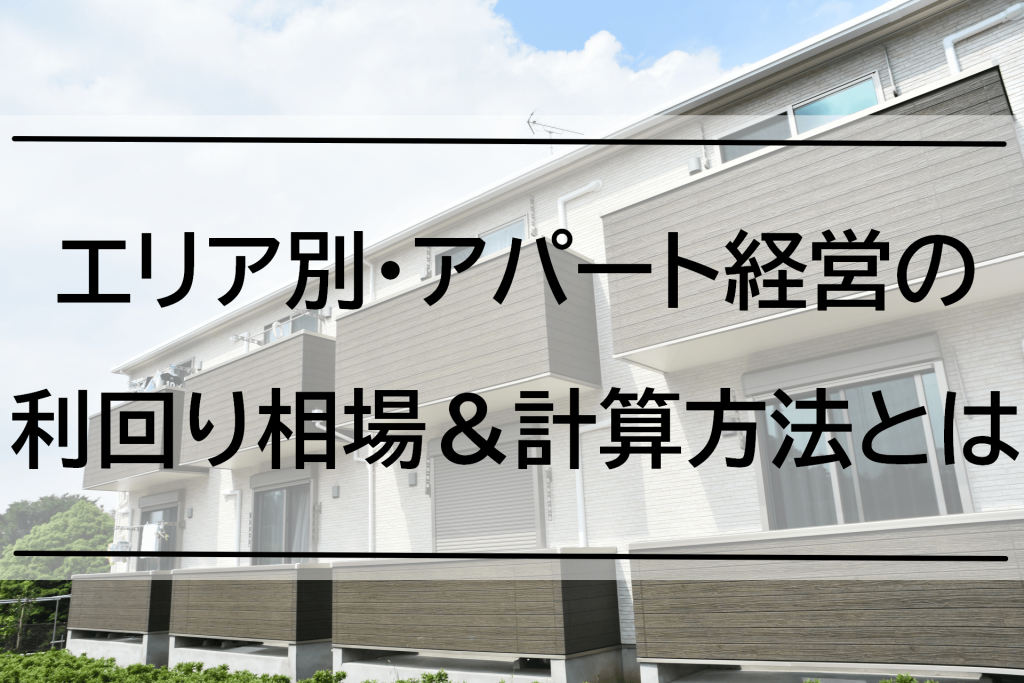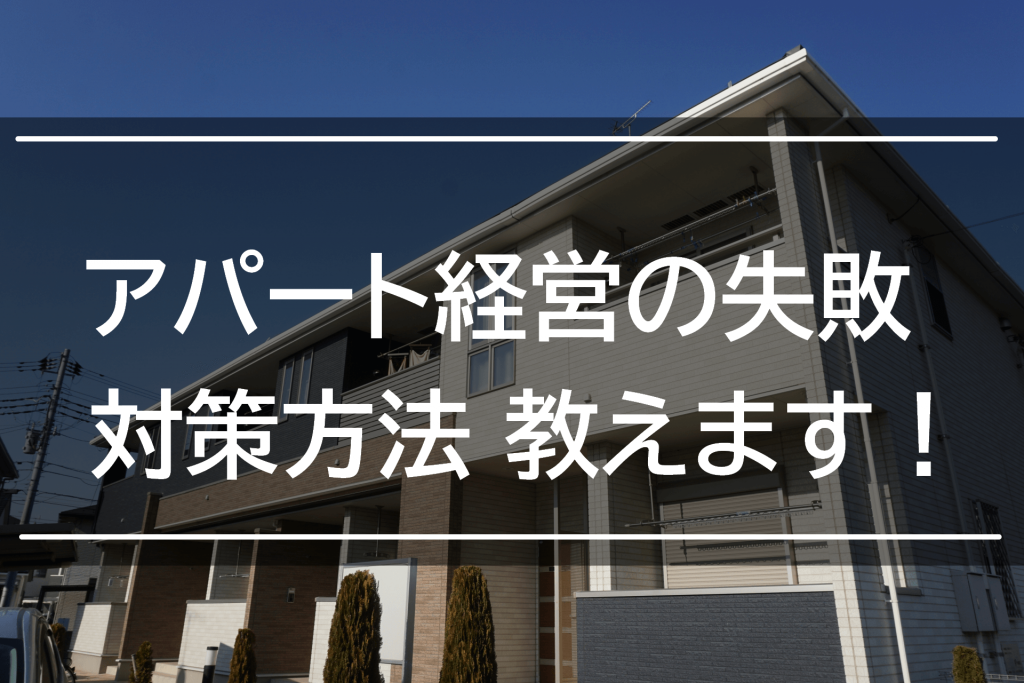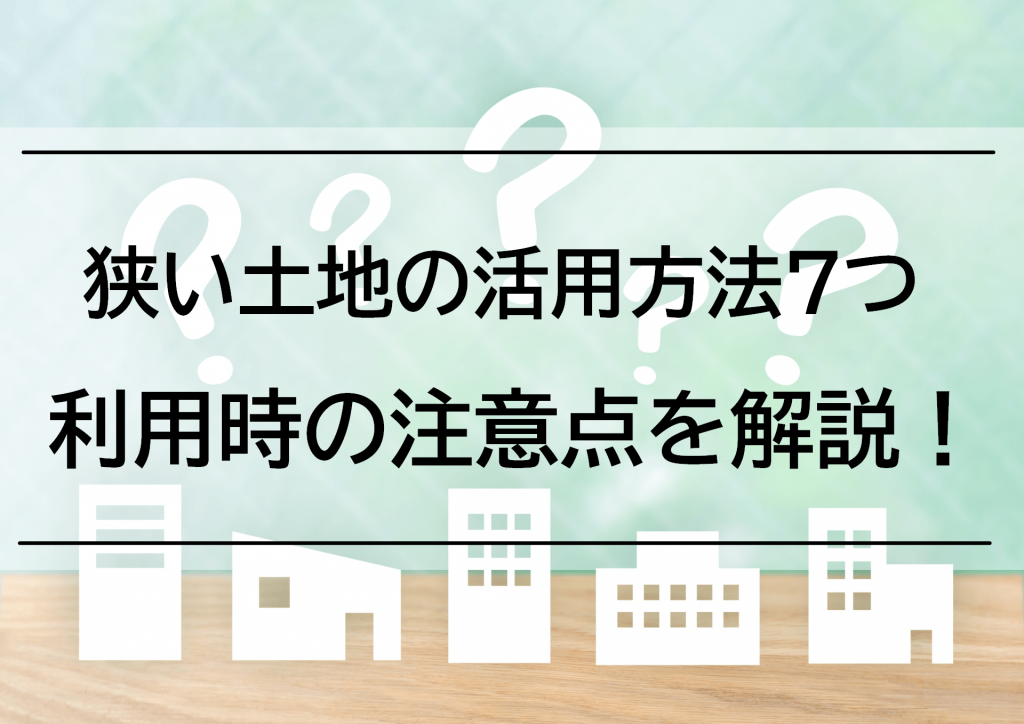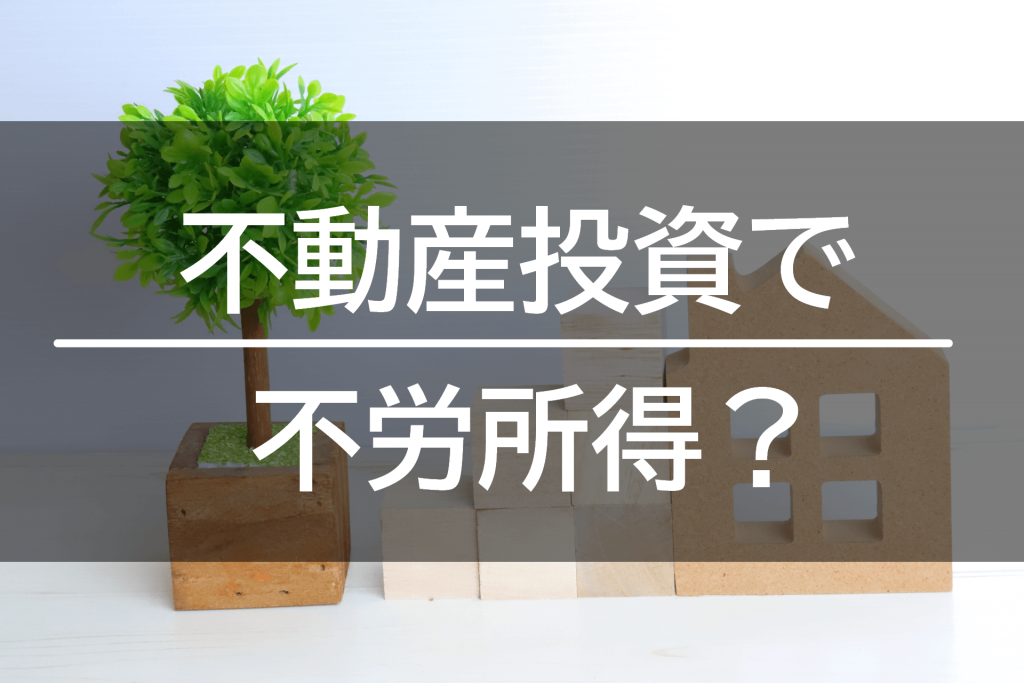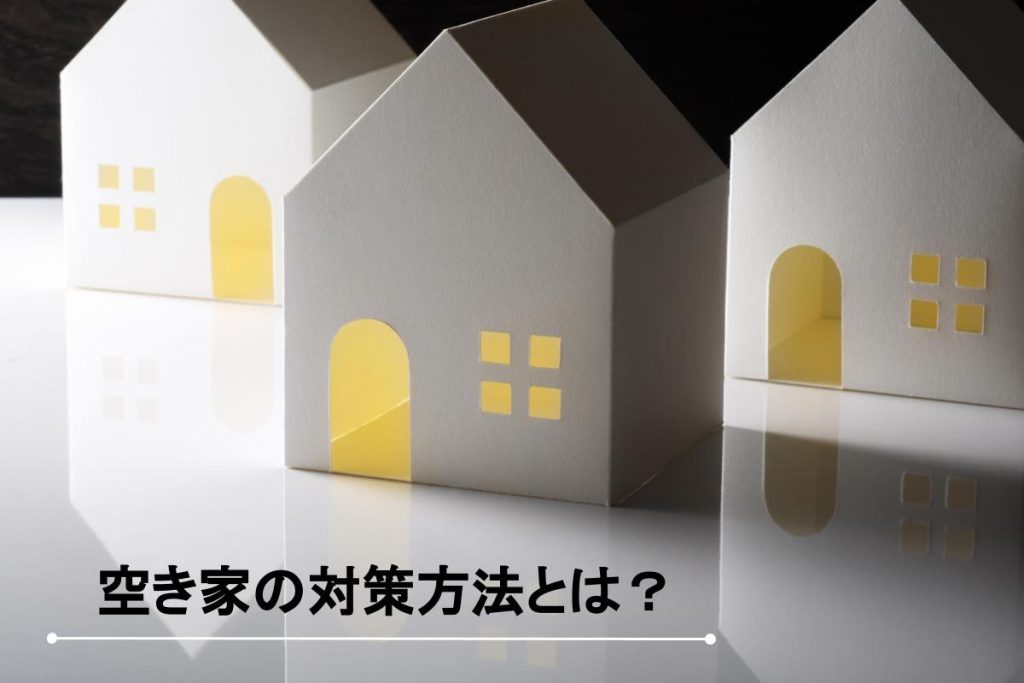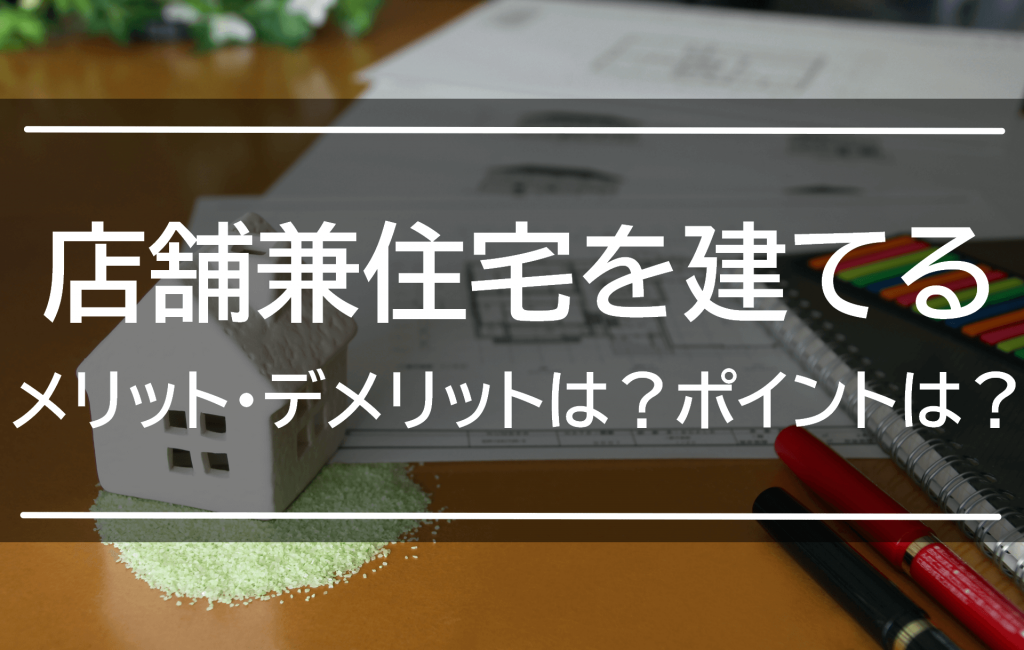※当記事はアフィリエイト広告を含みます。
アパート経営を始めるにあたって、「自己資金はいくら必要なのか?」は気になる点だと思います。
結論を先に述べると、アパート経営の自己資金比率は物件価格の約20%が最低でも必要になります。
具体的に言えば、物件価格が8,000万円のアパートであれば、1,600万円が自己資金として必要ということですね。
この記事では、なぜアパート経営の自己資金比率が最低でも20%必要なのかという根拠について解説していきます。
また、アパート経営の初期費用やローンの頭金なども紹介するので、しっかり読み進めてくださいね。
もしアパート経営について順番に学んでいきたいのであれば、アパート経営の基本の流れをまとめた下記記事もしっかり読んでおいてください。
「アパート経営に興味があるけど、何から始めてよいか分からない」この記事では、これからアパート経営への参入を検討している方向けに、アパート経営の基本的な流れを解説します。「アパート経営の不安を解消したい」「アパート経営に関する基礎知識を身につけたい」そんな方に、おすすめしたい内容になっています。
アパート経営の自己資金比率が最低20%になる理由

最初にお伝えしますが、「アパート経営の自己資金が最低でも物件価格の約20%」というのは、物件のみで判断した場合の話になります。
すでに大量の資産を持っている人であれば、自己資金をもっと少なくしてもアパート経営をすることは可能です。
とはいえ、自己資金の比率が約20%以上であればアパート単体での運営を目指せるので、資産が多い人にも役に立つ話です。
金融機関は返済能力をしっかり見ている
アパート経営の自己資金の比率を考える上で一番重要なのは、「あなた自身の返済能力が金融機関からどのように評価されるのか」という点です。
当たり前ですが、金融機関はあなたにお金を貸すかどうかを検討する際に、「貸したお金はちゃんと利子つきで返ってくるのか?」という点を見ています。
先ほど述べた通りお金持ちの人であれば返済能力が高いので、金融機関の審査は多少緩くなります。一方でそうでない人にはしっかりと物件の収支を見た上で、融資の判断を行います。
そして、金融機関が物件の収支を見る上でチェックするポイントの1つが、実質利回りです。
実質利回りを簡単に説明すれば、アパートの利益(売上-費用)が物件購入費用の何%であるかを表した数値です。
アパートの物件売買情報や建築シミュレーションでよく使われる、表面利回り(アパートの売上が物件購入費用の何%であるか)とは異なるので注意して下さい。
アパート経営の利回りの計算方法について分かっていない方は、下記記事をしっかり読んでおいてください。
アパート経営では、どれだけの利益を得られるかは気になるポイントですよね。 判断する基準のひとつとなるのが「利回り」ですが、きちんと理解しておかないと表面上の数字に振り回されてしまいます。この記事ではアパート経営の利回りについての基礎や、計算方法を実際の数値でご紹介します。
金融機関が売上(表面利回り)ではなく利益(実質利回り)を重視するのは、アパートの収益から返済できる金額の上限が利益であるからです。
よって金融機関があなたに貸し出せる金額の上限は、アパート経営の想定される利益から判断されるのです。
想定される利益から借入上限額は逆算される
先ほど金融機関が利益(実質利回り)を重視すると述べましたが、実際に実質利回りはどれくらいが想定されるのでしょうか。
アパートの立地や物件の築年数にもよりますが、一般的には4%〜6%程度が実質利回りとなります。
例えばアパートの購入費用が5,000万円だとすれば、想定される年間利益は200万円〜300万円ということになります。
では、仮に年間200万円〜300万円をそのまま返済額に当てるとしたら、一体いくらまで借入することができるのでしょうか。
オリックス銀行の公式サイトには「お借り入れシミュレーション」があるので、そちらを使って下記条件で計算してみました。
| 借入金額 | 4,000万円 |
|---|---|
| 返済期間 | 22年(※1) |
| 金利 | 3.00%(※2) |
(※1)木造住宅の法定耐用年数である22年で返済すると想定しています。
(※2)アパートローンの金利は2.5%〜3.5%あたりが多くみられたため、平均3%を採用しました。
すると、年間の返済額が約249万円という結果になりました。これは、5,000万円のアパートで想定される年間利益である200万円〜300万円の中間になります。
すなわち、5,000万円の80%にあたる4,000万円を借りた時点で、想定される年間利益と年間返済額が大体同じになるということです。
これ以上借入金額を増やしてしまうと利益よりも返済額の方が大きくなってしまうため、金融機関はリスクが高いと判断します。
そのため、上記のような条件で金融機関から借りると想定した場合、最低でも物件価格の20%の自己資金が必要になるのです。
もちろん、その他の資産や借入の状況によっては、自己資金が20%以上求められる場合もあるので注意してください。
とはいえ、金融機関の視点に立って言えば、自己資金は最低でも20%欲しいということは理解できたと思います。

上記の仮定は老朽化による運営費用の増加を考えていないので、将来的なリスクを考えると自己資金はアパート価格の30%〜40%程度あるのが望ましいです。
アパート経営をする上で必要な初期費用
アパート経営をする上で必要な初期費用は、大きく「アパート建設費」と「アパート建設費以外」の2つに分けられます。
そのため、ここでは具体的にどのような初期費用がかかるのかを説明していきます。
アパート建設費用
アパート建設費用は、これから紹介する「アパートの構造」と「アパートの規模や設備」によって大きく異なります。
アパートの構造
アパートの構造とは、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などのことです。
アパートとなると、一般的には木造や鉄骨造が多いかと思いますが、それぞれの平均坪単価は以下の通りです。
ハウスメーカーによっては、坪単価以外に「工事費」が含まれます。
アパートの規模や設備
アパートの戸数や階段、間取りや設備などによってもアパート建設費用は大きく変わってきます。
アパートの規模や設備は建設地の周辺ニーズによっても異なるため、一概に「どのくらいの規模でどのような設備を取り付ければ良い」とは言い切れません。
そのため、周辺ニーズを調査し、どのようなアパートを建設すれば採算が見込めるのか考えてみましょう。
アパート建設費以外に必要な初期費用
ここでは、アパートの建設費以外にどのような初期費用がかかってくるのかを具体的に説明していきます。
現地測量費は30万円程度
アパート建築費以外に、30万円程度の「現地測量費」がかかります。
アパートを設計するためには、敷地の真北や高低差の情報が必要なのですが、これらを測量することを「現況測量」と言います。
現況測量図がない場合は、基本的に設計士の指示の下、現況測量を行わなければいけません。
地盤調査費用は1ポイント当たり50万円程度
アパート建築費以外に、1ポイント当たり50万円程度の「地盤調査費用」がかかります。
アパートの構造や地盤の状態によっては、杭工事を行わなければいけません。
しかし、杭工事を行うためには、まず支持地盤の深さを把握する「地盤調査」を行う必要があります。
地盤調査も基本的に設計士の指示の下、行わなければいけません。
印紙代は請負工事金額によって異なる
アパート建設費以外に「印紙代」がかかるのですが、印紙代は請負工事金額によって異なります。
契約金別に見た印紙代は以下の通りです。
| 本則税率が適用される場合 | 軽減税率が適用される場合 (2014年4月1日~2020年3月31日までに契約を結んだ場合) |
|
|---|---|---|
| 1000万円超5000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
設計料は工事費の1%~3%
アパート建設費以外に工事費に対して1%~3%の「設計料」がかかります。
工事費が高いと設計料は1%になり、工事費が安いと設計料は3%になる傾向があります。
水道分担金は300万円程度
アパート建設費以外に300万円程度の「水道分担金」がかかります。
水道分担金とは、水道の利用申し込みを行う際、水道局に納付するお金です。
水道分担金は、戸数が多ければ多いほど高くなります。
基本的にハウスメーカーが事前に調査してくれているため、予め提案書に記載されています。
火災・地震保険料は請負工事金額の0.05%程度
アパート建設費以外に請負工事金額の0.05%程度の「火災・地震保険料」がかかります。
火災保険に関しては、一括で長期契約した方が安くなるため、資金に余裕があれば一括の長期契約がおすすめです。
新築建物登録免許税は固定資産税評価額によって異なる
新築のアパートを建てる場合、所有保存登記のために「新築建物登録免許税」がかかります。
所有保存登記とは、新たに取得した不動産に対して行われる所有権登記のことです。
新築建物登録免許税は以下の計算式で求められます。
- 固定資産税評価額×0.4%=新築建物登録免許税
ちなみに、課税標準額である建物の固定資産税評価額は、新築工事費の50%前後と言われています。
抵当権設定登録免許税は債権金額によって異なる
アパート建設費以外に「抵当権設定登録免許税」がかかるのですが、これは債権金額によって異なります。
アパートローンを組む場合、土地と建物に抵当権の設定登記を行う必要があるのですが、このときに抵当権設定登録免許税がかかります。
抵当権設定登録免許税は以下の計算式で求められます。
- 債権金額(課税標準額)×0.4%=抵当権設定登録免許税
司法書士手数料は7万円程度
アパート建設費以外に7万円程度の「司法書士手数料」がかかります。
基本的にアパートの保存登記と抵当権の設定登記は、自分で行うのではなく、司法書士に依頼するのが一般的です。
新築建物不動産取得税は固定資産税評価額によって異なる
新築のアパートを建てる場合、「新築建物不動産取得税」がかかるのですが、これは固定資産税評価額によって異なります。
新築建物不動産取得税は以下の計算式で求められます。
- 固定資産税評価額(課税標準額)×3%=新築建物不動産取得税
ただ、アパートの住宅床面積が40平米以上240平米以下である場合、不動産取得税の軽減措置が受けられます。
軽減措置が適用される場合の新築建物不動産取得税の求め方は以下の通りです。
(1戸あたりの固定資産税評価額-1200万円)×3%=新築建物不動産取得税
融資関連費用は10万円程度
アパートローンを組む場合、事務手数料や保証料などの「融資関連費用」がかかります。
事務手数料は融資を受ける際、銀行に支払う手数料で、10万円程度が相場です。
しかし、保証料は借入金額や借入年数によって異なるため、注意しましょう。
入居者募集費用は賃料の1ヶ月~6ヶ月
アパートを竣工する場合、賃料1ヶ月分~6ヶ月分の入居者募集費用がかかります。
管理委託方式で管理を委託している場合の手数料は家賃1ヶ月分が相場ですが、空室保証の管理方式を採用している場合の手数料は家賃3ヶ月分~6ヶ月分が相場です。
アパート経営をするために必要なローンの頭金

アパート経営をするにあたって、ローンを組む方がほとんどかと思いますが、頭金はいくら用意すれば良いのでしょうか。
ここでは、ローンを組む場合、頭金はいくら用意すれば良いのか具体的に説明していきます。
頭金は購入金額の1割程度用意しておくのが理想
アパートローンを組む場合、頭金は物件購入金額の1割程度用意しておくのが理想です。
木造アパートの場合、法定耐用年数は22年と言われていますが、新築アパート投資の融資期間は20年~35年で設定されることがほとんどです。
アパートの法定耐用年数を超えた融資になると同時に、新築アパートはワンルームマンション投資に比べて購入金額が3倍~4倍高くなります。
そのため、頭金は物件購入金額の1割程度、余裕があれば2割程度用意しておいた方が良いでしょう。
金利は3%前後が一般的
アパートローンの金利に関しては、2%~3%が相場です。
しかし、頭金の金額によっては金利を交渉できる場合があります。
「少しでも安い金利でローンを組みたい」と考えている場合は、頭金を2割~3割ほど用意しておくと良いでしょう。
融資限度額は資産価値の50%程度
アパートローンの融資限度額は、アパートの資産価値の50%程度が相場です。
ローンを組む金融機関によって幅がありますが、「60%以上も可能」という金融機関はまず存在しません。
もしも、「60%以上も可能」と謳っている金融機関があった場合は、基本的に疑った方が良いでしょう。
手元に残しておきたい資金

アパート経営は、ワンルームマンション投資と比べると、空室リスクや家賃下落リスクが高い投資です。
そのため、想定利回りを下回る場合や赤字の月が出てくる場合もあるでしょう。
また、オーナー自身が失業してしまう場合や健康状態が悪化してしまう場合もあるかと思います。
そのようなことを踏まえると、最低でも半年、できれば1年間収入がなくても生活していけるほどの資金を手元に残しておいた方が良いと考えられます。
まとめ
今回は、「アパート経営をしていく上で必要な資金」について解説してきました。
アパート経営は少ない自己資金で始められますが、それによりオーバーローンになってしまったりローンを返済できなくなってしまったりしては元も子もありません。
そのため、最低でもアパート購入費用の約20%、できれば約30%〜約40%ほどの自己資金を用意することをおすすめします。
また、不測の事態に備えて半年~1年分の生活費を手元に残しておくこともおすすめします。
アパート経営は失敗した時の影響が大きく、取り返しのつかない事態になってしまうこともあります。
アパート経営が失敗するパターンや対策は下記記事にまとめているので、不安を解消しておきたい人はぜひ読み進めてください。
この記事では失敗しないアパート経営のために、事前に知っておきたい失敗事例や失敗に至った理由、失敗しないための対策をご紹介します。これからアパート経営に取り組む方は、チェックしてみてください。