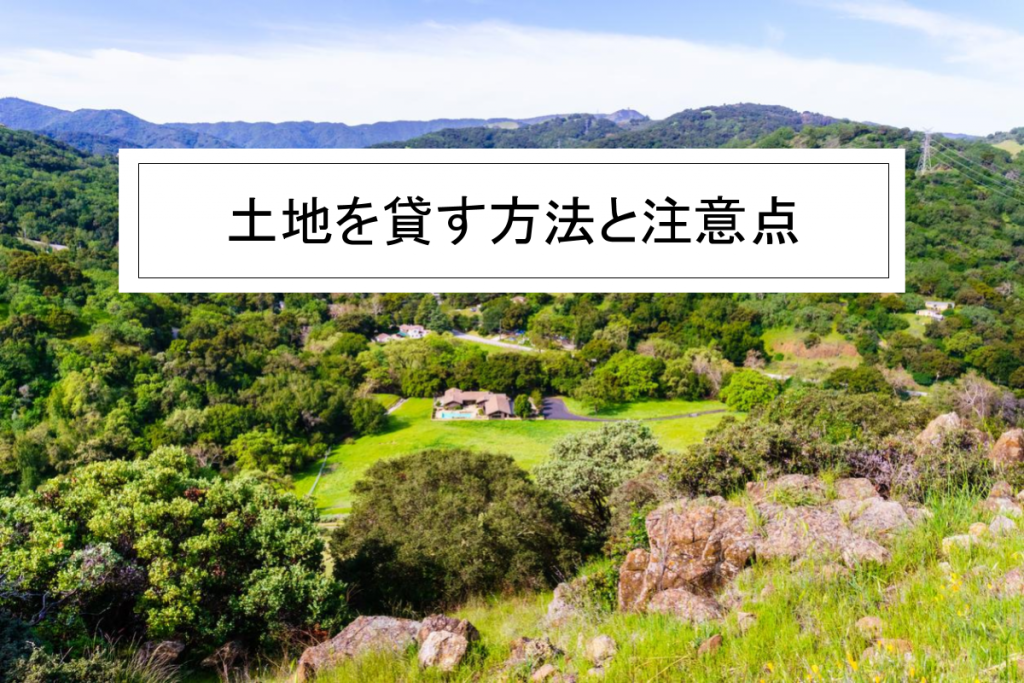※当記事はアフィリエイト広告を含みます。
「不動産投資で減価償却をして節税になるってどういう仕組み?」
「減価償却の計算方法が知りたい。」
不動産投資では、減価償却をうまく利用することで節税効果が期待できます。
不動産投資をするならば、減価償却の仕組みや計算方法を理解しておきましょう。
ここでは、不動産投資の減価償却費について、減価償却の計算方法や手順、注意するポイント、原価償却を利用して節税効果を得るポイントについて解説します。
不動産投資において減価償却は欠かせない知識なので、計算方法や手順をマスターしておきましょう。
不動産投資における減価償却費とは

不動産投資をしている人ならば、減価償却という言葉を耳にしたことがあるでしょう。
不動産投資では、効果的に節税をして収益を生み続けることが大切です。
「聞いたことはあるけれど、減価償却にどんな意味があるのかわからない」と言う方は、これを機に減価償却についての知識をつけておきましょう。
そもそも減価償却とは
減価償却とは、価格が大きく長期間に渡って使用できる物は、購入した年に全額を費用計上せずに一定の期間に渡って分割して費用を計上することです。
つまり、不動産投資のために5,000万円のマンションを購入した場合、購入費用の全額を購入した年に経費として計上するのではなく、法定耐用年数に応じて費用として計上するということです。
5,000万円のマンションは1年で価値が無くなってしまうような消耗品ではなく、年々価値が下がってはいくものの何十年にも渡って利益を生み出すものなので、価値がある期間は継続して経費計上することで正確に収益を把握することができるのです。
このように減価償却によって計上される費用を、減価償却費と呼びます。
不動産投資で減価償却が大切な理由

不動産投資で減価償却を正しく行うと、節税に効果があります。
節税目的で不動産投資を考えているのなら、なぜ減価償却が節税に効果的なのかを理解しておきましょう。
減価償却費は経費計上できる
減価償却費は、一定期間に渡って経費として計上できますが、実際に支出を伴わないという性質があります。
不動産投資では利益に対して税金がかかるので、収益が多ければ多いほど所得税が高くなりますが、減価償却費を一定期間計上し続けることで実際の収益を少なく見せることができるので節税効果があるのです。
同じ経費でも、交際接待費などは実際に支出を伴う経費なので使えば使うほどに手残りも減ってしまいます。
一方で、減価償却費は費用を計上することで、利益を少なく見せ税金額を減らすことができるのに、実際に支出を伴わないので正しく使えば手残りを増やすことができるのです。
損益通算で節税効果がある
不動産投資で減価償却をすると損益通算を利用して節税することができます。
損益通算とは、不動産投資の赤字額を給与の黒字から相殺して計算することをいいます。
例えば、建物価格が5,000万円の不動産を所有していて、減価償却費1,000万円、家賃収入800万円、必要経費120万円、給与所得が900万円と仮定して考えてみましょう。
この場合、不動産所得は、家賃収入800万-必要経費120万-減価償却費1,000万=320万となり帳簿上は320万円の赤字となります。
この損失額を給与所得900万円と損益通算すると、給与所得の900万-不動産所得の赤字額320万=580万となり、所得額が900万円から580万円に圧縮されることになります。
日本は累進課税制度で所得が多ければ多いほど課税税率が高くなる仕組みになっているので、所得額を抑えることで節税になるのです。
所得税の税率は下記の通りです。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税局 所得税の税率
このように、課税所得が900万円を超えると税率が33%と大幅にアップするので、課税所得が900万円を超える方は、不動産投資で損益通算を行えば大幅な節税につながることになります。
こちらの記事では、「不動産投資の経費対象や節税のポイント」について解説しています。
不動産投資で減価償却が必要なケース

不動産投資での減価償却が必要な場合は、下記の2パターンあります。
それぞれのパターンについて解説します。
不動産収入がある場合
不動産投資をして不動産収入が発生した場合は減価償却が必要となります。
不動産投資では、必要経費の中でも減価償却費の支出割合が大きいので重要です。
法定耐用年数などの情報を元に計算しましょう。
投資用ではなく、自宅用の不動産については収入が発生しないため減価償却の計算や申告は不要となります。
物件を売却する場合
不動産投資物件を売却する際にも減価償却が必要となります。
投資物件などの不動産を売却して売却益が出た場合は譲渡所得税がかかります。
不動産の売却益のことを譲渡所得と呼び、譲渡所得に一定の税率を掛けて計算をした譲渡所得税がかかります。
譲渡所得は、不動産の売却代金から、不動産購入費用や売却したときの費用を差し引いて計算されます。
この不動産の取得費は土地と建物分を分けて計算するのですが、建物は経年劣化で価値が減少すると考えられるため減価償却費相当額を差し引く必要があります。
物件を売却する場合には、建物の費用から減価償却費を差し引く作業を忘れないよう注意しましょう。
不動産の減価償却の計算方法

減価償却の計算方法では、定額法・定率法を用いて計算をします。
どの計算方法を用いるかによって、経費の計上方法が変わるのですが、一般的には定額法を用いて計算するケースが多いので覚えておきましょう。
ここではそれぞれの計算方法を紹介します。
定額法
定額法では、固定資産の法定耐用年数の期間、毎年同額の減価償却費を計上します。
減価償却費は、取得原価に対して耐用年数に応じた償却率を掛けて求めることができます。
- 定額法の減価償却費=取得価額×定額法の償却率
償却率とは、アパートの建築や購入費を1として、それを耐用年数で割った値のことで具体的な数値は下記の通りとなります。
| 建物構造 | 耐用年数 | 償却率 |
|---|---|---|
| 木造 | 22年 | 0.046% |
| 木造モルタル | 20年 | 0.050% |
| 鉄骨造3mm以下 | 19年 | 0.053% |
| 鉄骨造3mm超4mm以下 | 27年 | 0.038% |
| 鉄骨造4mm超 | 34年 | 0.030% |
| 鉄筋コンクリート造 | 47年 | 0.022% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 47年 | 0.022% |
建物の減価償却に関しては定額法で計算することが一般的で、平成10年4月1日以降に取得した建物に関しては、以前使われていた旧定額法、または現在使われている定額法のみで計算されます。
また、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備や構築物の償却方法についても、定額法のみが適応されることとなっています。
不動産投資で減価償却の計算をする場合は、定額法を覚えておきましょう。
定率法
定率法では、資産を取得した年は償却額が大きく、年々償却額が少なくなるという計算方法です。
建物は定額法で計算するとされていますが、定率法が選択可能な資産もあるので、状況によって使い分けましょう。
定率法では、最初の償却額が大きいので早めに経費として計算したい場合に用いることが一般的です。
定率法を選択するといったように、それぞれの状況に沿って最適な選択をする必要があります。
- 定率法の減価償却費=取得価額(or 未償却残高)×定率法の償却率
定率法は短期間に2度の税制改正が行われたので、同じ定率法でも固定資産の購入時期によって、減価償却の計算方法が変わります。
- 平成19年4月1日以後に取得した固定資産:定額法or250%定率法
- 平成24年4月1日以後に取得した定率法を使う固定資産:定額法or定率法(200%定率法)
なお、定率法を使って経費を計上するには、変更しようとする年の3月15日までに税務署への届け出が必要になります。
不動産の減価償却費を計算する実際の手順
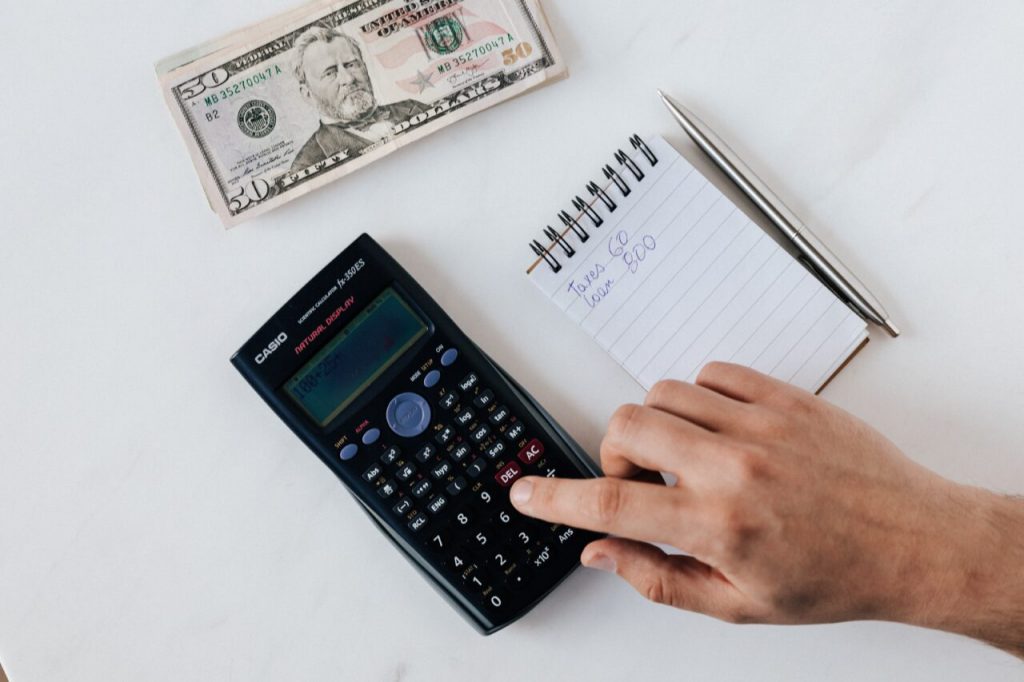
不動産などの固定資産は消耗品ではないので、減価償却費として使用する年数に応じて少しずつ費用として計上する必要があります。
建物に限らず、原則として10万円以上で使用期間が1年以上のものは、その年に全額を費用として計上するのではなく減価償却費として計上することとされています。
ここでは、不動産投資で建物の減価償却費を計上する方法を実際の手順に沿って解説します。
土地と建物価格に分ける
減価償却費を計算する時は、まずは不動産の価格を土地と建物に分けます。
減価償却の対象となるのは価値が下がっていくものなので、不動産の場合土地は対象となりません。
売買契約書や譲渡対価証明書などに土地・建物それぞれの価格が記載されていればそれを参考にしましょう。
記載がなく建物部分の価格が分からない場合には支払った消費税から建物取得価額を算出します。
土地部分は非課税なので消費税から建物価格を逆算できます。
また、 固定資産税評価額を使って計算することもできるので、市区町村の窓口で固定資産評価証明書を取得し、建物と土地の固定資産税評価額を確認しましょう。
総額に対して建物の評価額が占める割合を計算し、実際の売買時の不動産価格に建物の評価額割合を掛けると建物の購入費用を算出することができます。
建物と附属設備を分ける
土地と建物の価格を分けたら、次に建物本体と建物の付随設備の購入価格を区別します。
建物本体を減価償却するのと同様に、建物設備にも減価償却は発生します。
建物の付随設備の償却額は建物本体に比べれば少額ですが、設備の種類に応じて耐用年数が個別に定められているので個別に減価償却しましょう。
建物以外で経費計上できるものと耐用年数の一例は以下の通りです。
| 構造又は用途 | 耐用年数 |
|---|---|
| 電気設備(蓄電池電源設備を除く | 15年 |
| 給排水衛生設備、ガス設備 | 15年 |
| 冷房・暖房・通風またはボイラー設備(冷暖房設備で冷凍庫の出力が22kw以下のもの) | 13年 |
| エレベーター | 17年 |
| エスカレーター | 15年 |
| 消火・排煙などの設備 | 8年 |
| 金属製のアーケード | 15年 |
設備の耐用年数が短くなることが一般的なので、付属設備を別で減価償却すると1年あたりの減価償却費を大きくすることができるので節税効果が期待できます。
法定耐用年数を調べる
次に物件の耐用年数を調べます。
耐用年数は建物の構造によって以下のように定められています。
| 構造 | 法定耐用年数 |
|---|---|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 47年 |
| 鉄筋コンクリート造 | 47年 |
| 鉄構造 | 34年 |
| 計量鉄構造 | 19年 |
| 木造 | 22年 |
法定耐用年数について知りたい方に向けて、こちらの記事で「鉄骨造の耐用年数や償却の計算方法」について解説しています。
中古物件の場合は残存耐用年数を算出する
中古物件の場合には、確認した耐用年数と取引時の経過年数から残存耐用年数を簡便法を用いて算出する必要があります。
簡便法は、不動産を中古で購入した場合に用いられる計算方法です。
中古物件では、合理的に耐用年数を見積り決定することが難しいので、便法による計上が認められていて、中古物件の価格が同等物件の新築価格の50%を超えていない場合にのみ適用できます。
耐用年数を算出する方法として、以下の2パターンがあります。
- 法定耐用年数を超えていない 耐用年数=(法定耐用年数-築年数)+築年数×20%
- 法定耐用年数以上の期間が経過している 耐用年数=法定耐用年数×20%
法定耐用年数を超えているかどうかで計算方法が変わるので覚えておきましょう。
減価償却費を計算する
上記で調べた数字を元に実際の減価償却費を計算してみましょう。
投資用不動産物件(土地3,000万円、建物価格3,000万円)の築15年の鉄筋コンクリート造のマンションを購入し定額法で減価償却費を計上する場合で考えてみましょう。
この場合は、定額法の減価償却費と中古物件の耐用年数が知りたいので、下記2種類の計算式を利用します。
- 定額法の減価償却費=取得価額×定額法の償却率
- 耐用年数=(法定耐用年数-築年数)+築年数×20%
3,000万円(建物価格)×0.022(定額法の償却率)=66万円となり、減価償却費は66万円となります。
減価償却期間は、鉄筋コンクリートの法定耐用年数が47年なので、(47年-15年)+15年×20%=35年が減価償却期間となります。
つまり、年間66万円の減価償却費を35年間経費として計上できることになります。
不動産投資の減価償却で注意する3つのポイント

減価償却はうまく利用することで節税効果が期待できますが、注意点もあることを覚えておきましょう。
ここでは、注意する3つのポイントについて解説します。
物件譲渡の際の税金が高くなる可能性がある
減価償却した建物を売却すると、譲渡所得税が高くなってしまう可能性があります。
譲渡所得に対して課税される譲渡所得税は、今まで減価償却してきた累計額を取得価額から差し引く必要があるため、減価償却費の額が大きければ譲渡所得税も高くなってしまうのです。
3,000万円で購入した不動産を3,000万円で売却した場合、利益は0円と思いがちですがそうではありません。
今まで減価償却費を計上した分だけ不動産の価値は減っているので、減価償却が終わって1円の価値の時期に売却した場合、3,000万円がそのまま譲渡所得となります。
物件の譲渡には、短期譲渡と長期譲渡の2種類があります。
- 短期譲渡:物件取得から6年以内に売却をした場合で譲渡税率は39%
- 長期譲渡:物件取得から6年を超えて売却をした場合で譲渡税率は20%
そのため、譲渡所得3,000万円に対して長期譲渡税率20%で計算すれば600万円の譲渡所得税がかかることになります。
適切な売却時を見極めるためにも、譲渡時期のシミュレーションをしておくことが大切です。
「譲渡所得税の計算方法」についてはこちらの記事で解説しています。
減価償却期間しか節税効果がない
減価償却は節税に効果がありますが、減価償却期間が終わればその効果はなくなります。
建物や設備ごとに耐用年数が異なるので、事前に減価償却期間が終わったあとの収支のシュミレーションをしておきましょう。
青色申告でなければ繰越控除ができない
確定申告には白色申告と青色申告がありますが、白色申告では損益通算は可能ですが、繰越控除はできません。
繰越控除とは、その年の損失を翌年以降の利益と相殺できる仕組みのことで、損益通算して100万円の赤字になった場合、翌年の所得から100万円の控除が可能となります。
青色申告では3年まで繰越控除できるため、節税効果が高まります。
青色申告は、「青色申告承認申請書」を事前に提出した事業者のみが行える確定申告の方式です。
白色申告に比べ有利な点が多いので、節税を考えるなら青色申告がおすすめです。
減価償却を利用した不動産投資節税方法

減価償却を利用して節税効果を高めるためには、下記の3つのポイントを意識しましょう。
もちろん、不動産投資では収益を生むことが第一の目標なので、節税にばかり目を向けるのではなくトータルの収益バランスを意識することが大切です。
中古の木造物件で不動産投資を行う
減価償却を利用して節税効果を高めるためには、中古の木造物件で不動産投資を考えましょう。
木造建物の法定耐用年数は22年です。
鉄筋コンクリート造のマンションは47年と倍以上あるので、建物価格や築年数が同じだった場合は木造マンションの方が減価償却期間が短くなるので、減価償却費を大きく取ることができるのです。
さらに、築年数が22年を超えた物件については、耐用年数×20%の金額で減価償却ができるので節税には最も効果的な物件ということになります。
長期譲渡で税率を抑える
減価償却費で節税を考えるのなら、売却時期にも注意が必要です。
物件の譲渡には、短期譲渡と長期譲渡の2種類があり、物件取得から6年以内に売却した場合は短期譲渡で譲渡税率39%となり、6年を超えて売却した場合は長期譲渡となり譲渡税率20%となります。
税率が低い長期譲渡の方が、短期譲渡よりも節税には効果的になります。
「長期譲渡所得税の計算方法や節税方法」については、こちらの記事で解説しています。
高収入であるほど節税効果が高まる
不動産投資においては、年収1,200万円以上の人は節税効果が高い傾向にあります。
年収1,200万円を超えると、基礎控除や配偶者控除などの各種所得控除の合計を引いた課税所得額は約900万円程度となるので所得税率は33%となります。
不動産購入から5年以降に売却すると譲渡所得税率は約20%となるので、その差は13%分を節税できることになります。
一方、課税所得900万円以下の人は23%となり、譲渡所得税率20%と3%しか変わらないので、節税としてのメリットは少ない上、不動産投資のリスクを背負うことになってしまいます。
課税所得が高くなればなるほど、所得税率が高くなるので譲渡所得税との差が広がるので節税効果が高まります。
減価償却の知識を活かして不動産投資をしよう
減価償却の知識は不動産投資をする上で欠かせません。
法定耐用年数期間内に正しく費用として計上することで、正確な収支を把握することができる上に、節税効果を高めることもできます。
不動産投資を行うなら、減価償却の知識を活用して節税効果を高めましょう。